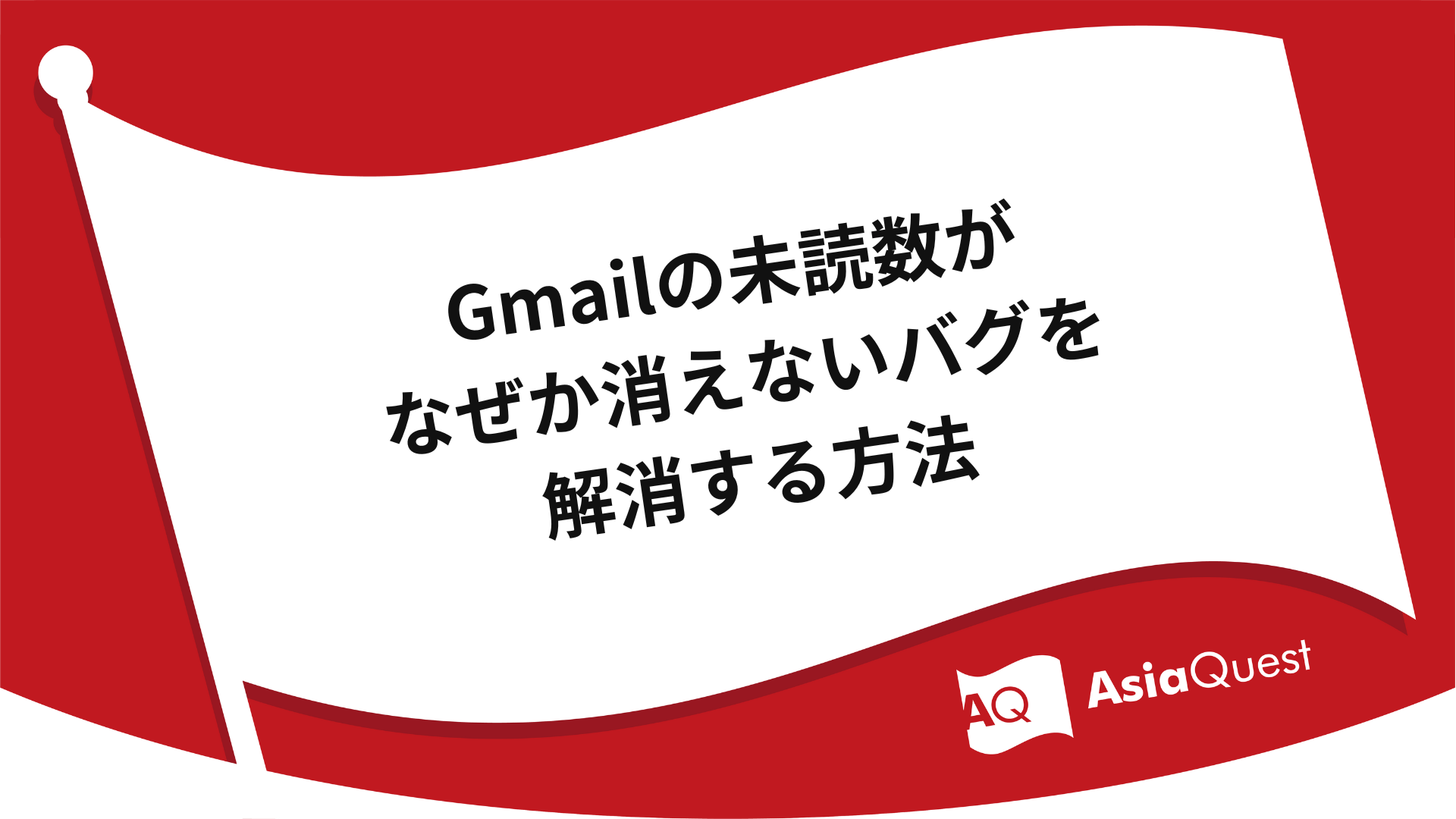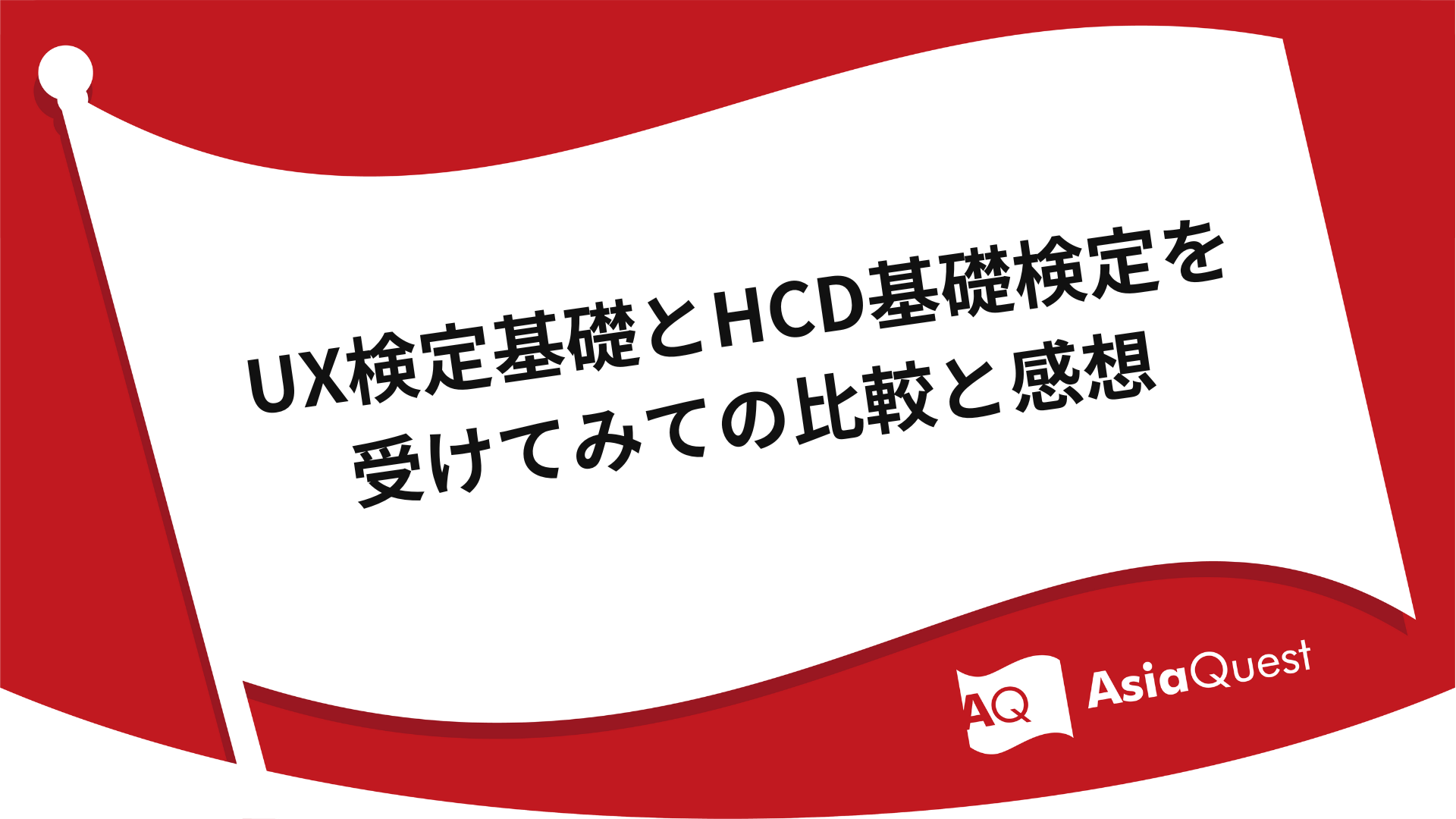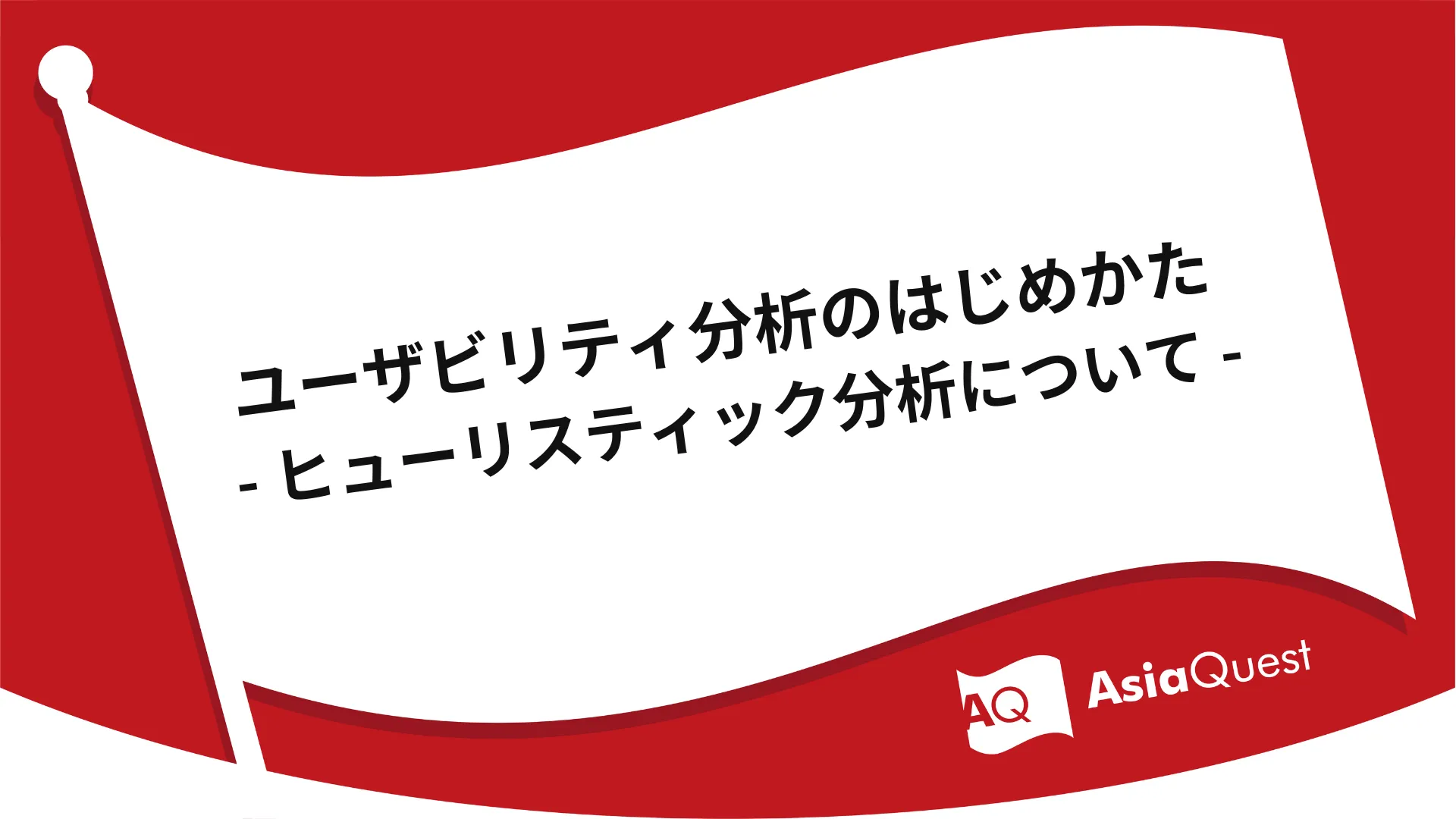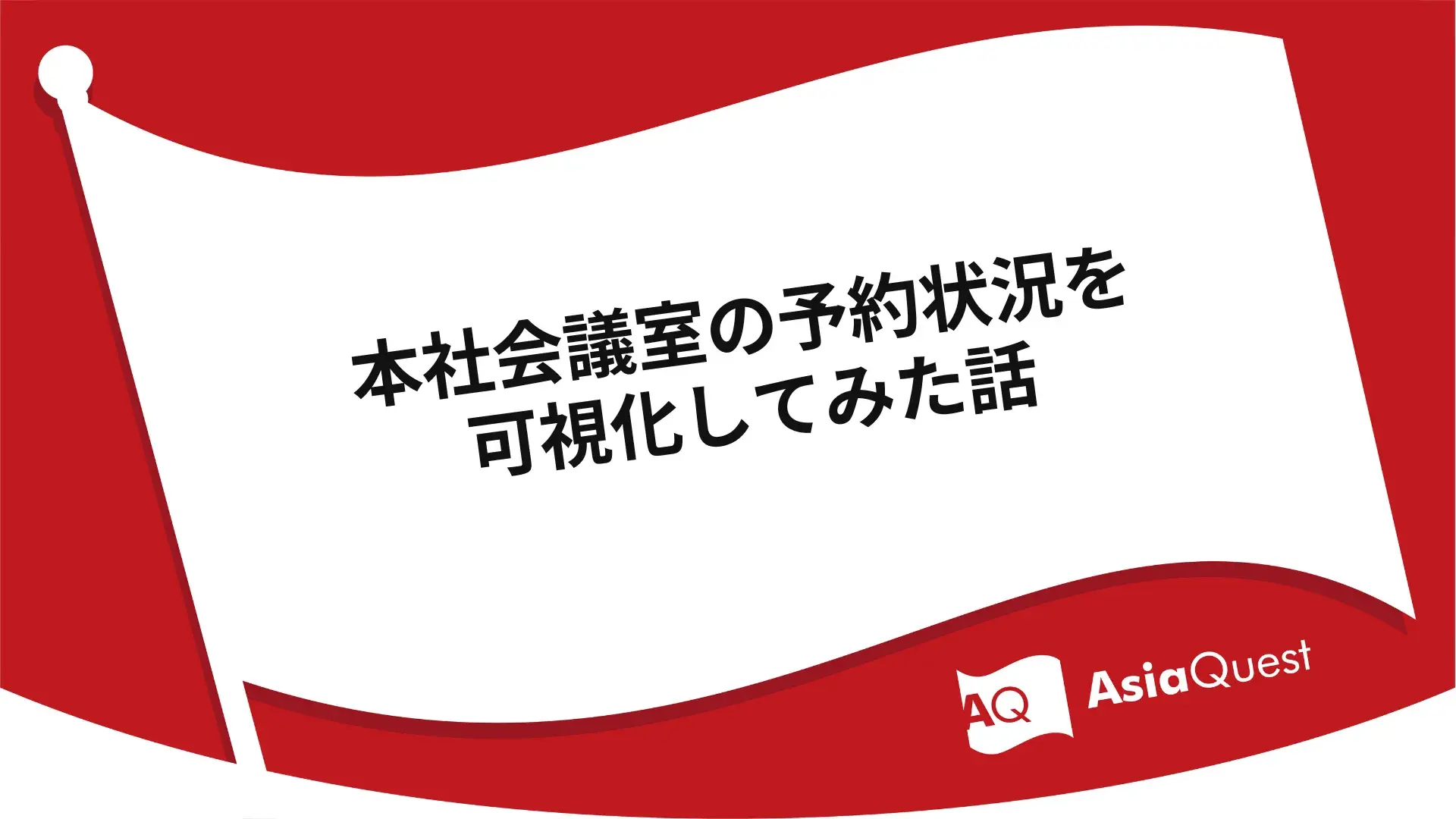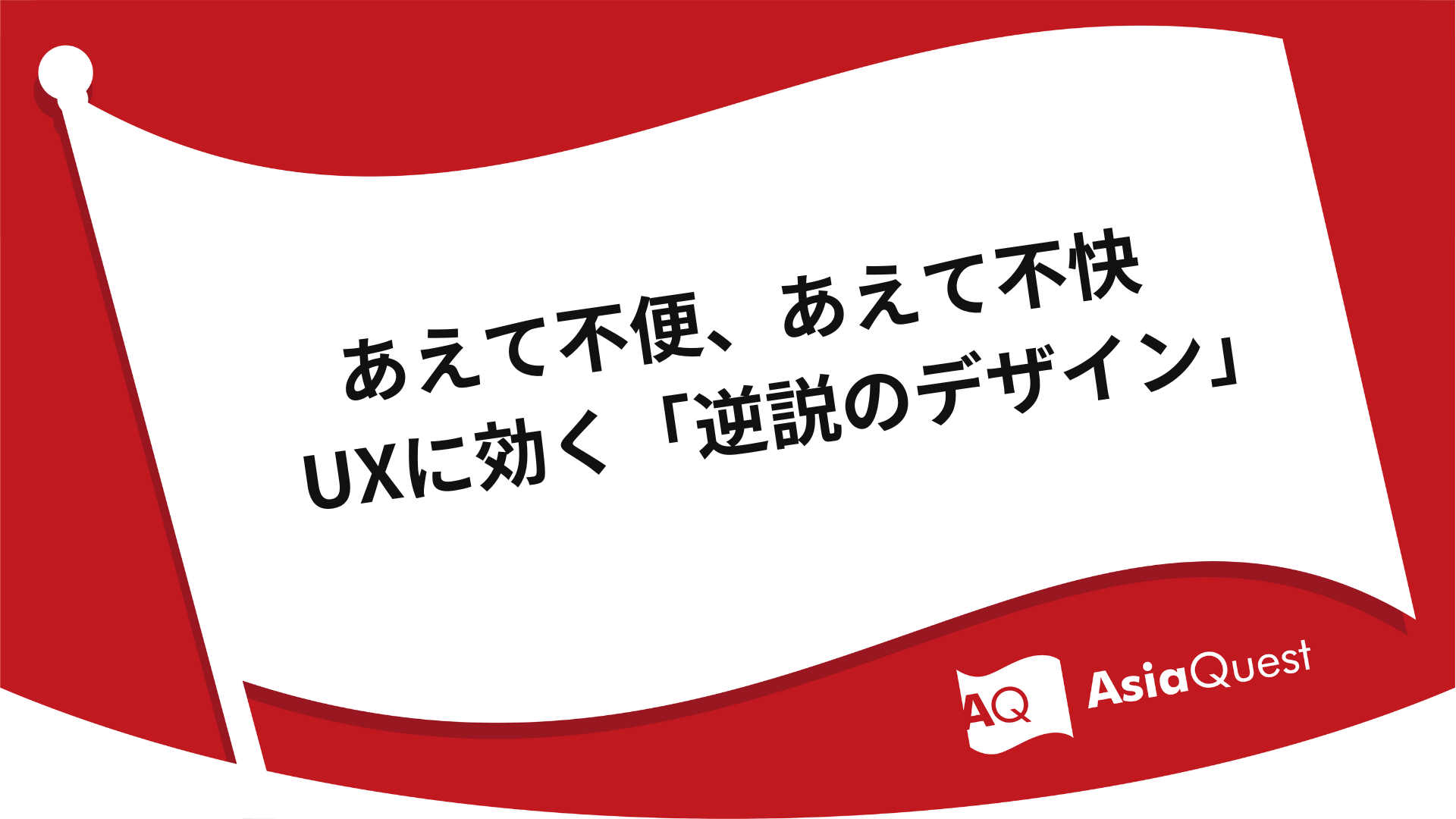子育てから学ぶUXデザイン - 新米パパが気づいた「本当のユーザー目線」-
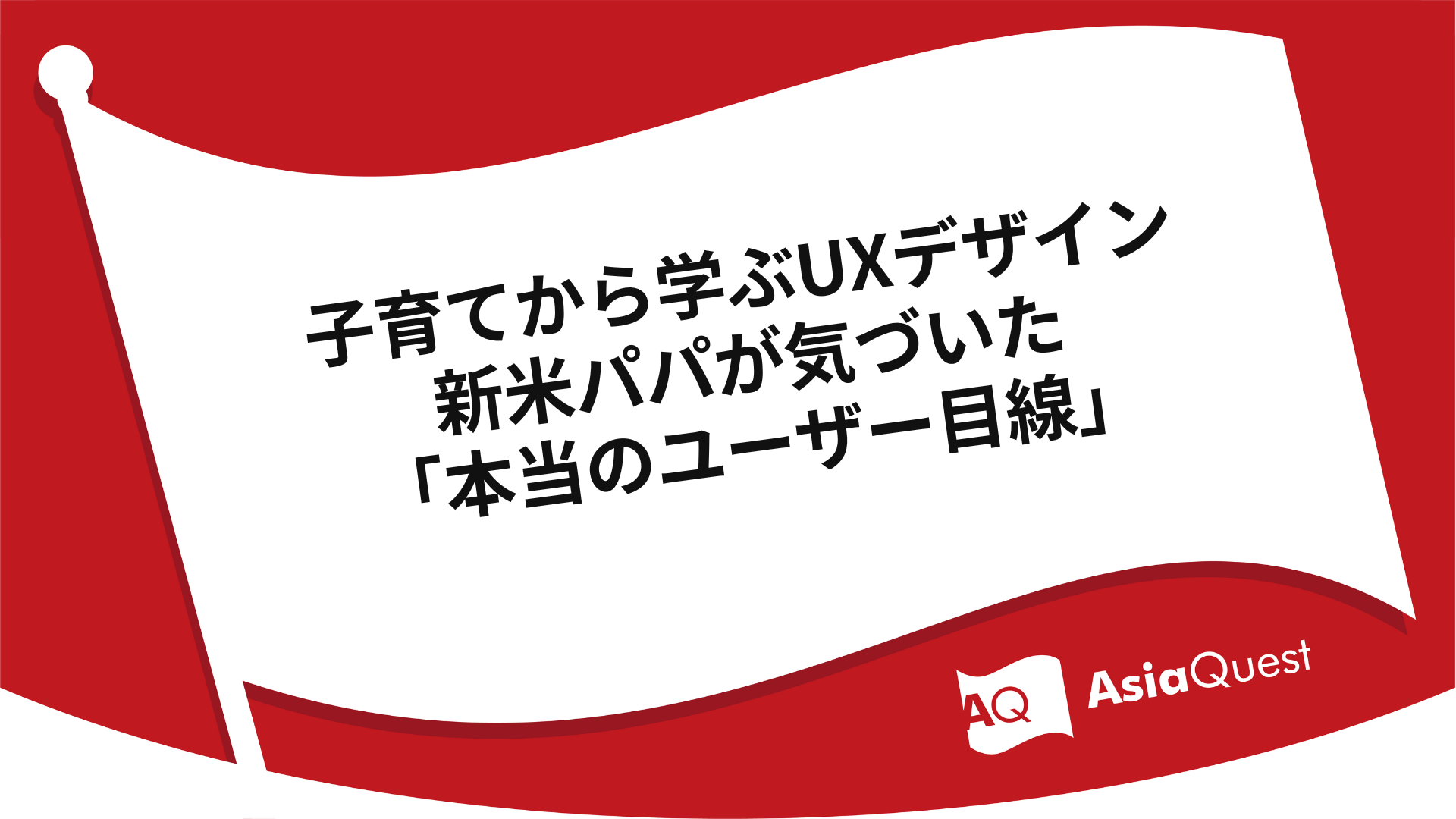
目次
はじめに
デジタルエンジニアリング部の花井です。
普段はエンジニアリングやプロジェクト管理の仕事をしながら、UI/UXについての発信や勉強会を社内外で行うなど、UI/UXの大切さを少しずつ伝えるような活動をしています。
執筆記事:UX検定基礎とHCD基礎検定を受けてみての比較と感想
今回は、そんな私が「子育て」というまったく新しい体験を通して、改めてUXの本質を見直すきっかけになった出来事について書いてみたいと思います。
赤ちゃんとの生活の中で感じた「これはUXだ!」という瞬間を、みなさんと共有できたらうれしいです。
子ども用の服に学ぶUXの本質
私には現在1歳3ヶ月の子どもがいます。第一子ということもあり、子育ては本当にわからないことだらけです。
ベビーカーって、こんなに種類あるの!?
おむつって、こんなに頻繁に替えるの!?
「寝たな」と思ったのに…寝てなかった!!
…と、発見と驚きの連続の毎日です。
そんな中で、「あ、これUXだな」と思った出来事がありました。それは子どもに肌着を着せていたときのことです。

なんと、乳児用の肌着は縫い目が外側にあるんです(すべての商品がそうというわけではありませんが)。
普段、大人の服は縫い目が内側にあるので、「あれ?裏返しで着せちゃったかな?」と思ってしまう。
でもそれは赤ちゃんの肌を守るための設計で、見た目よりも肌触りを優先しているわけです。
これってまさに、ユーザー(=赤ちゃん)の特性に寄り添ったUXだと感じました。
普段、自分たちが当たり前に使っているものも、使う人が変われば設計も変わる。
UXはユーザーの数だけ形がある、ということを改めて実感しました。
ちなみに、乳幼児の服はボタンが多く掛け違えるケースが多いので、途中で間違えても気づけるようにボタンの色を変えることでどのボタンが対になってるかすぐに分かるようになってるんですが、あれ、地味にありがたいです!

ユーザーが変われば最適なUXも変わる
上の例からも分かるように、モノやサービスを作るときに大切なのは、「誰のためのものか?」をちゃんと考えることだなと改めて思いました。
特に乳児のように、繊細で、言葉では伝えられないユーザーが相手になると、ほんの小さな違和感がそのまま体験(UX)に直結します。
でもこれは、子どもに限った話ではなくて。
大人だって、「言語化しない・できない不満」って日常にたくさんありますよね。
だからこそUX設計では、「声なき声」にどう気づくか? がすごく重要になってくると思います。
以下では、子育てでの気づきを例にしながら、「声なき声」を拾うための実践的なアプローチをいくつか紹介してみます。
① 行動観察(ユーザビリティテスト/シャドーイング)
実際の行動を観察することで、言葉にされないニーズを探る方法です。
うちの子は、「お腹がすいた」と「お母さん」を、どちらも「まんま」と呼んでいた時期がありました(かわいい)。
なので、言葉だけでは判別できず、しぐさや表情、時間帯などの "文脈" から推測する必要があります。
ちなみに「パパ」は今のところパパ専用です(笑)
② データからの気づき(ログ/ヒートマップ/定量分析)
数字も"声"のひとつ。
データからユーザーの状態を読み取る方法です。
いつもなら同じ時間にミルクを欲しがるのに、今日は飲みたがらない…?
そんなときは「もしかして体調悪いかも?」といった気づきにつながります。
予測とズレた行動=何かが起きてるサインかもしれないんです。
③ “間接的な声”の収集(サポート/レビュー/ママ友)
自分では気づいていないけど、他の誰かが代弁してくれる声を拾う方法です。
SNSで見かけたアイデアグッズに「うわ、これめっちゃ便利じゃん!なんで今まで使ってなかったんだろう…」って思ったこと、ありませんか?
それって実は、自分も感じていた不満を“他人の声”で初めて自覚したということだと思います。
④ エスノグラフィー的な共感(当事者として体験する)
自分自身がユーザーと同じ立場になって体験し、感覚的な気づきを得る方法です。
今回の子育ても、まさにそうでした。
たとえば、赤ちゃん用のスプーンで高温になると色が変わるものがあります。
実際に使ってみると、ご飯を食べさせるときに赤ちゃんの様子に気を配りながらでも、瞬時に温度がわかるのはとても助かりました。
「赤ちゃんにご飯を食べさせるのは大変そうだ」と想像することはできますが、実際に体験してみて初めて、そこにある負荷や工夫の意味がリアルにわかるということも多いと感じています。
共感は、想像ではなく体験から生まれる。それを実感しています。
実際のUX設計でも活用されるいくつかのアプローチを、子育てでの具体的な気づきと照らし合わせて整理してみました。
下の表は、「声なき声」をどう拾い取るか?という視点で、方法・目的・子育てでの発見をまとめたものです。
| アプローチ | タイプ | 目的 | 子育てでの気づき |
|---|---|---|---|
| ユーザビリティテスト | 質的 | 行動のズレを発見する | 泣く/飲まない/触らない=UIの詰まり |
| ログ・ヒートマップ分析 | 量的 | 詰まりや離脱を可視化する | ミルク時間のズレ=体調や気分の変化 |
| サポート・レビュー分析 | 準質的 | 共通の"言語化されない悩み"を発見 | ママ友やSNSの声で気づく不満 |
| エスノグラフィー(共感) | 主観的 | 同情ではなく共感を得る | ご飯を食べさせる時の難しさを実感 |
以上のように、子育ての中には言葉にならないサインに気づくためのヒントがたくさん詰まっています。
そしてその中でも、特に強く感じているのが——
赤ちゃんは、ある意味ユーザーテストのプロだということです。
言葉で文句を言うことはないけれど、"飲まない""泣く""じっと見つめる"。
その一つひとつの行動が、明確なUIへのフィードバックになっていると感じます。
子育てを通して、言葉にされないユーザーの気持ちにどう寄り添い、気づけるか?
そんなUXの本質を、毎日のように教えられている気がしています。
弊社の取り組み
アジアクエストでも、子育てと仕事の両立を応援する動きが少しずつ広がっています。
最近では育休を取得する社員が増えたり、家族をオフィスに招待して職場を体験してもらう「ファミリーデー」が開催されたりと、育児をしながらでも働きやすい環境づくりが進んでいます。
実際に自分が子育てをしてみると、「仕事をする環境」や「チームの理解」がどれほど助けになるかを、ひしひしと感じます。
子育ては、決してラクなものではありません。
でも、UXの視点で日常を見つめ直すことで、小さな気づきがたくさん得られる体験でもあります。
そんな気づきを、プロダクト開発やプロジェクト運営にも活かしていくことで、より使いやすく、人にやさしいシステムづくりにつなげられると信じています。
おわりに
子育てを始めてから、「ユーザー体験」というものが、急にぐっと身近になった気がしています。
赤ちゃんは言葉で要望を伝えてはくれないけれど、泣いたり、飲まなかったり、触れなかったりと、行動のひとつひとつが、ものすごく正直なフィードバックです。
そんな“究極のユーザー”と向き合う中で、「ユーザーの声をどう拾うか」「どんな設計がやさしいのか」を、これまで以上に考えるようになりました。
子育てを通じて得たこの気づきを、これからのプロダクト開発やチームづくりにも、しっかり活かしていきたいと思っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
アジアクエスト株式会社では一緒に働いていただける方を募集しています。
興味のある方は以下のURLを御覧ください。