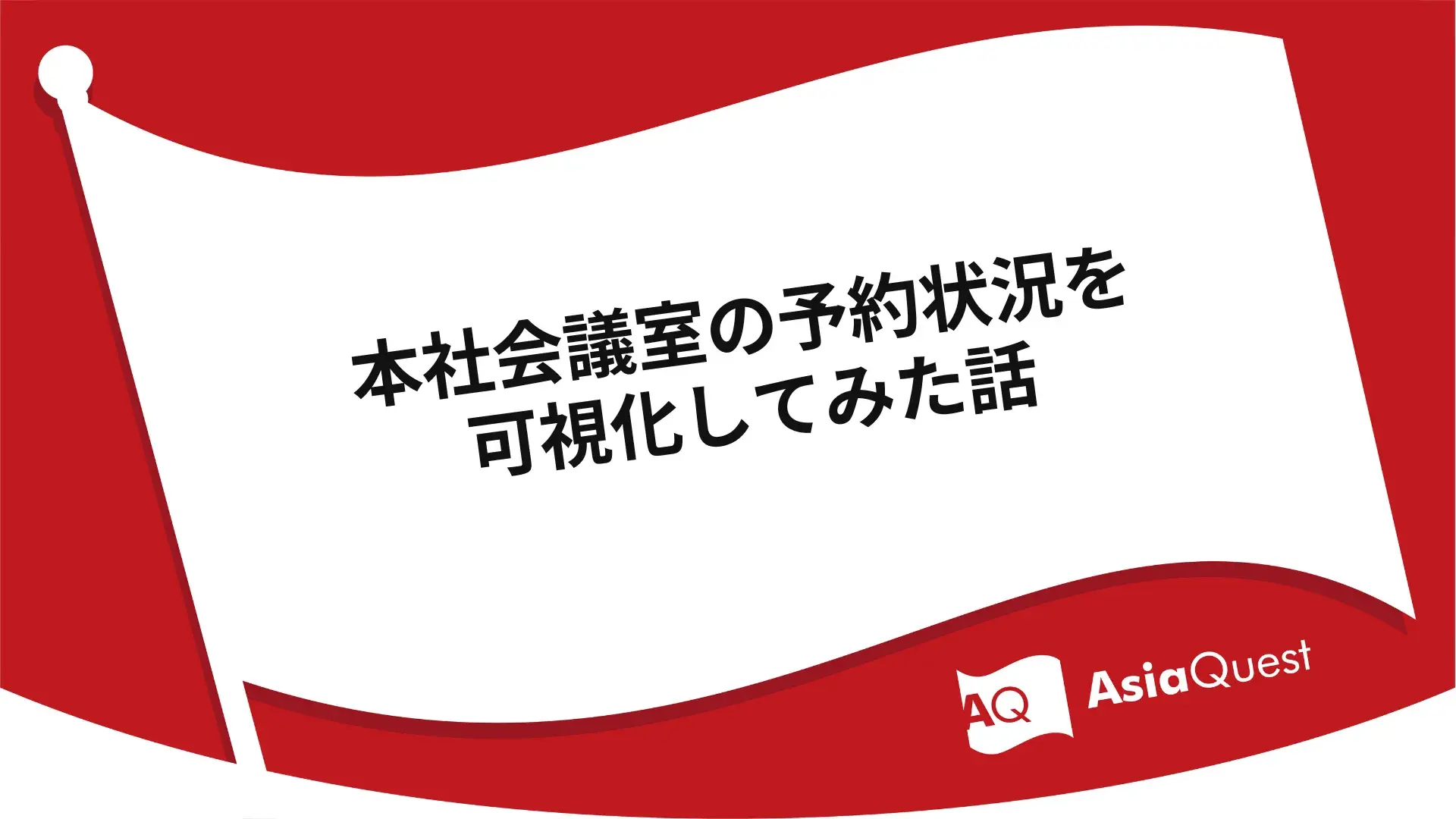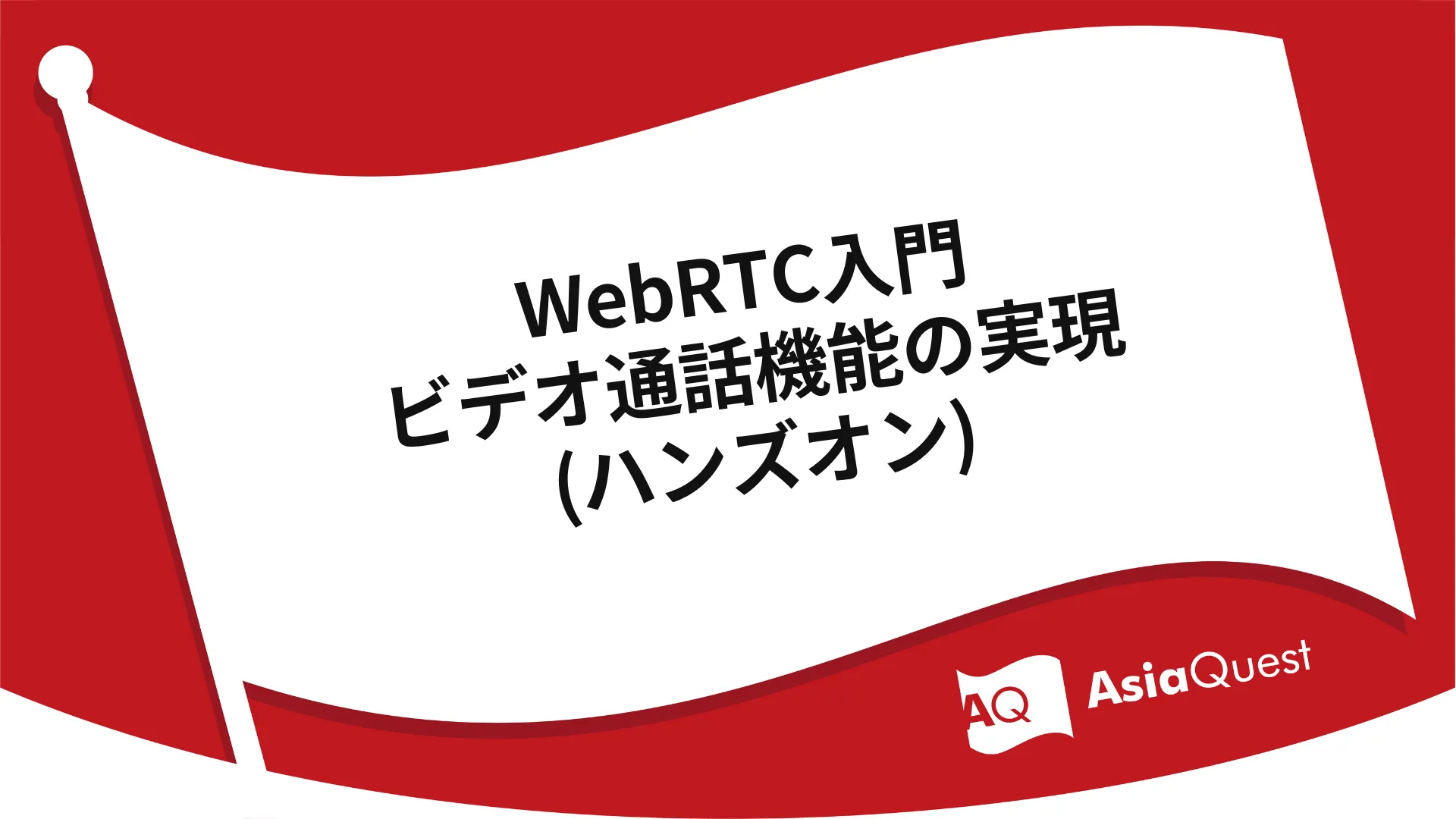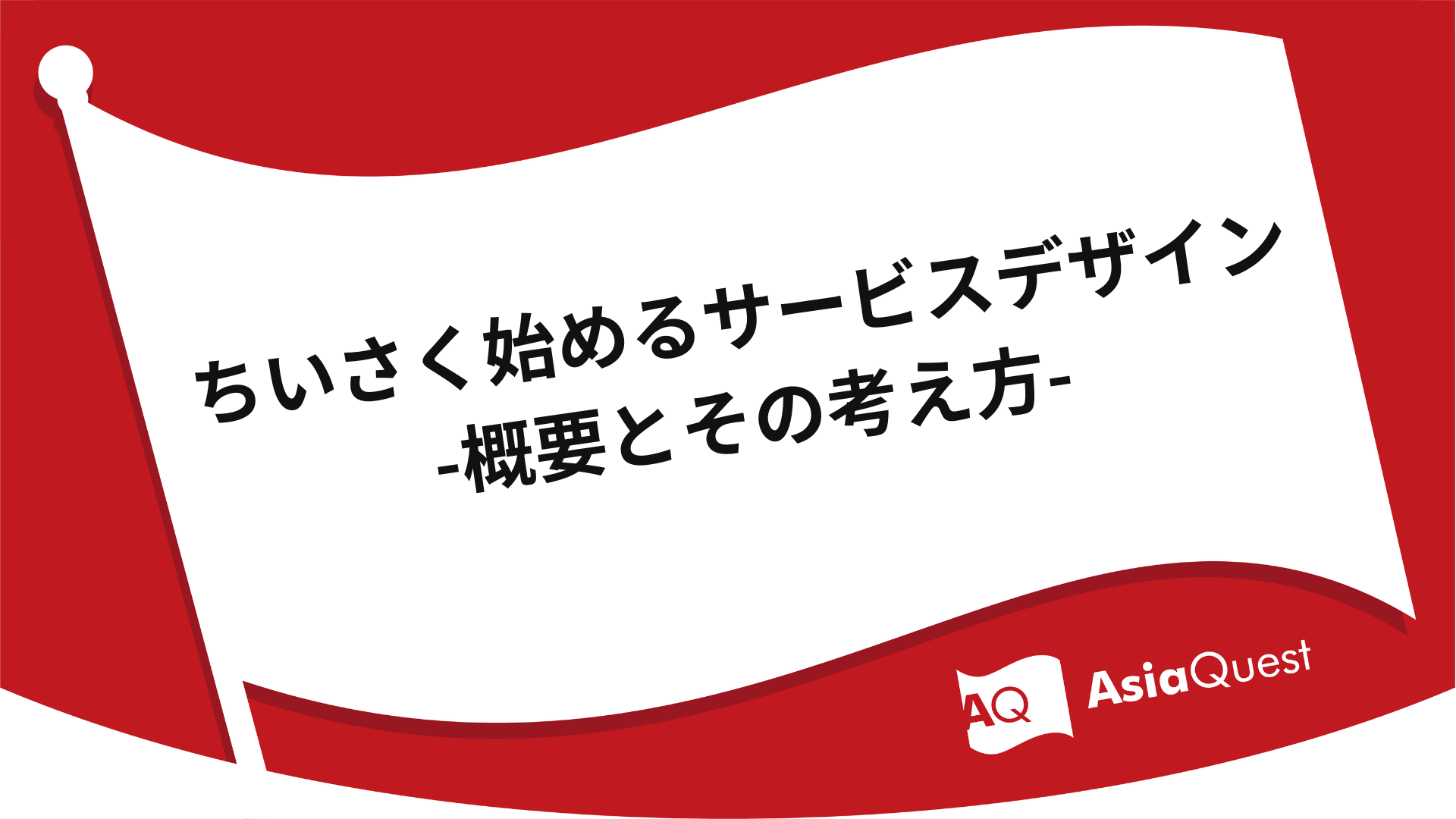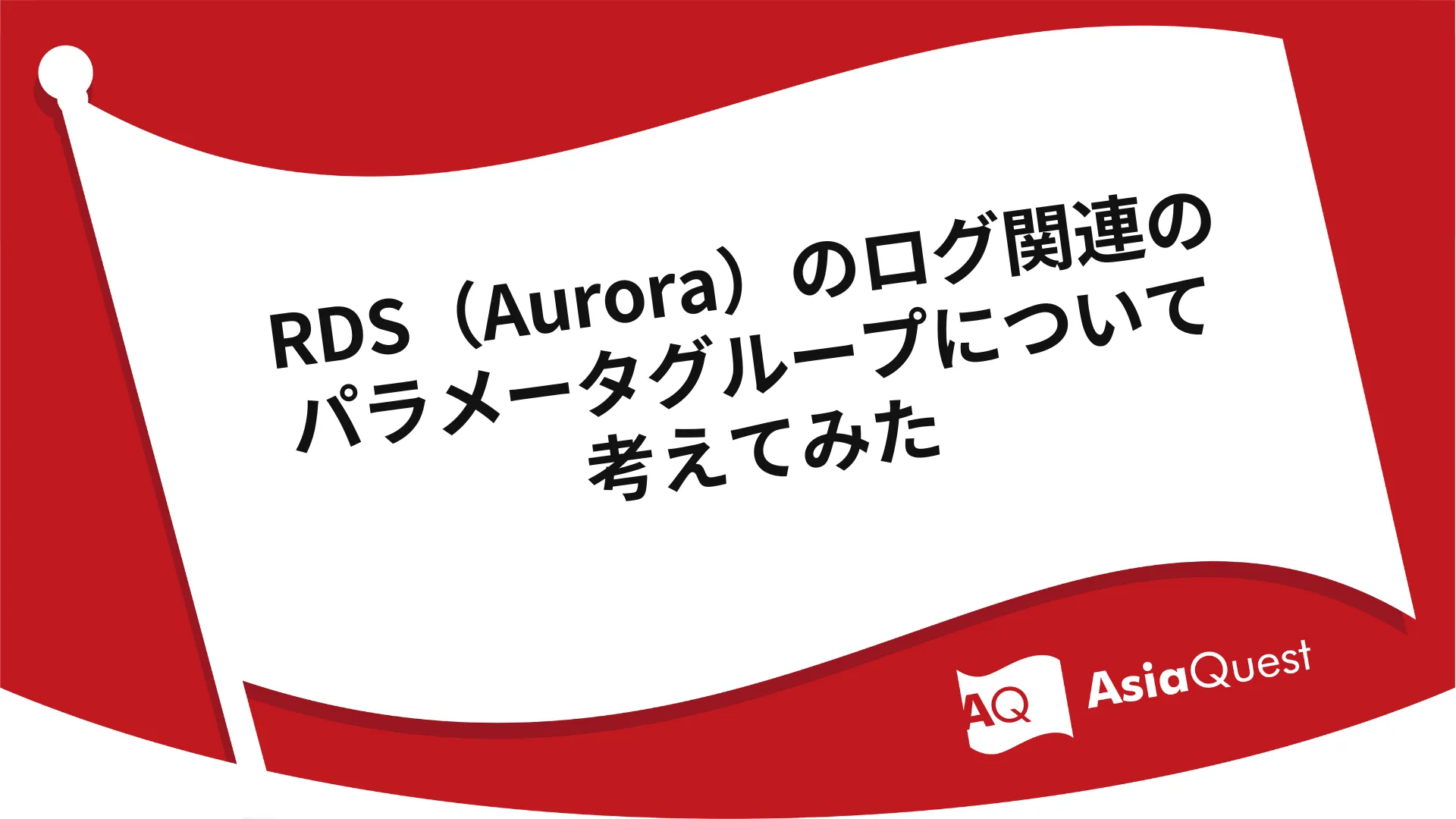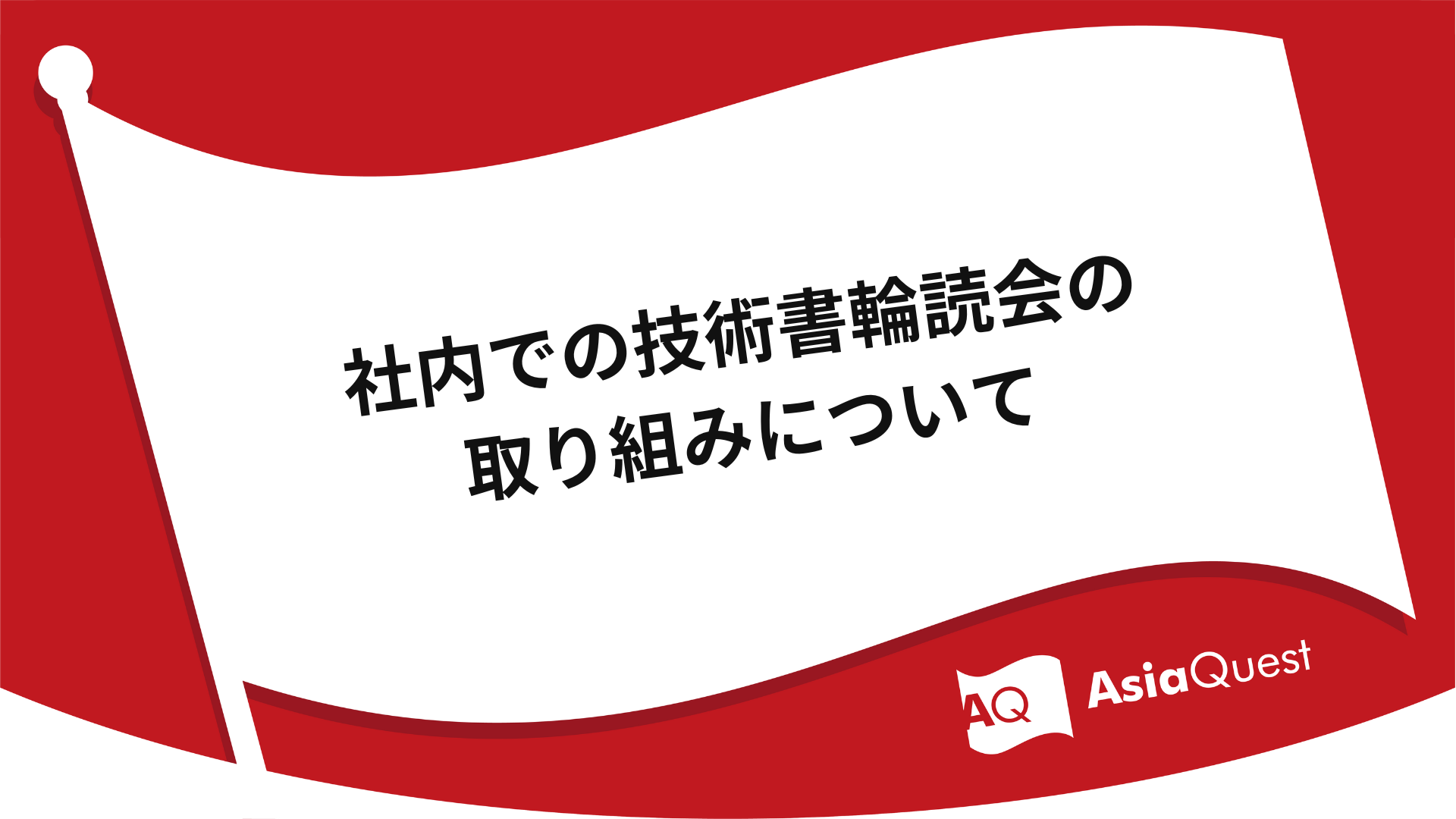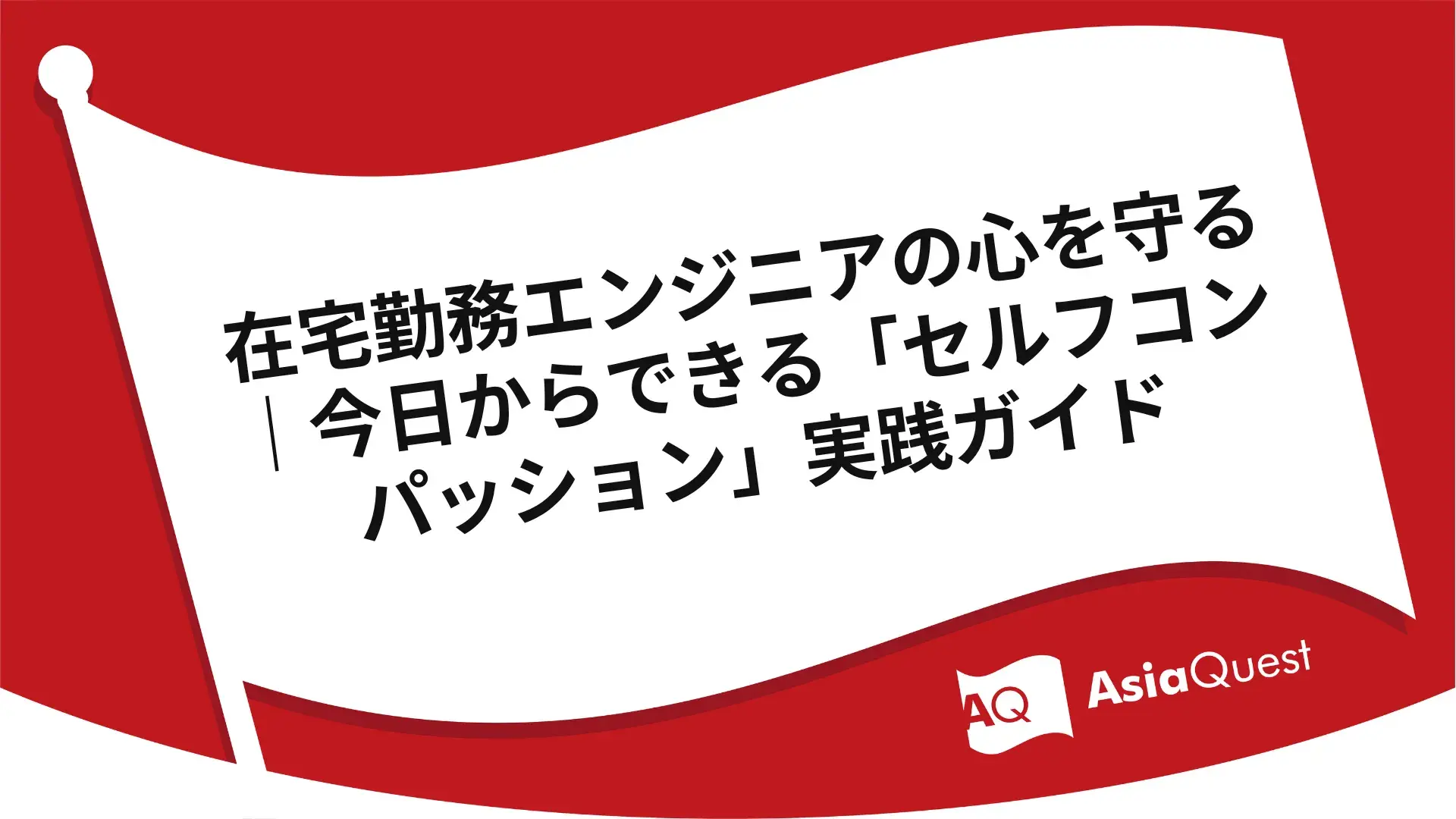あえて不便、あえて不快。UXに効く「逆説のデザイン」
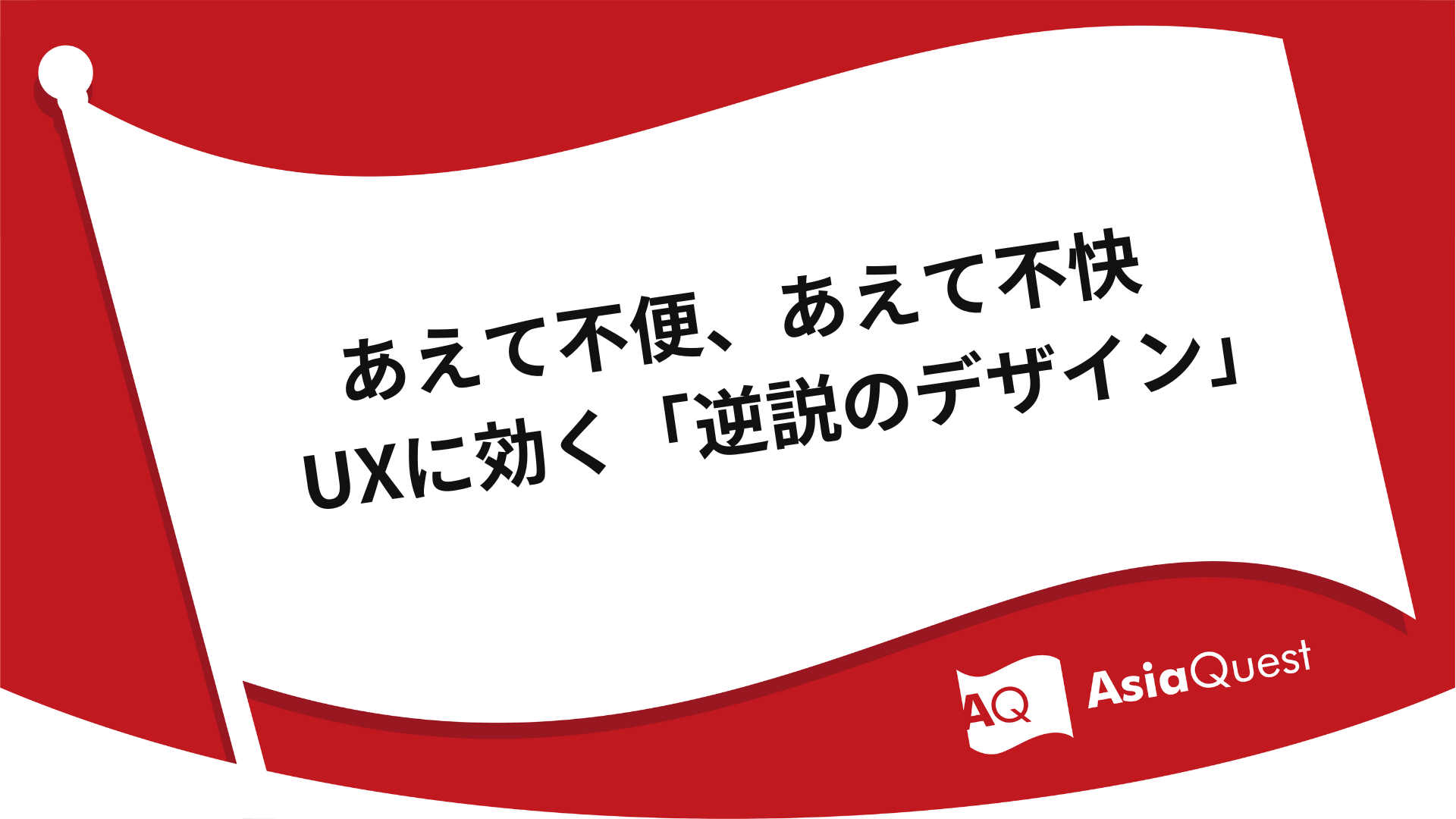
目次
はじめに
デジタルエンジニアリング部の花井です。
便利なものに囲まれていると、「これは本当に自分にとって使いやすいのか?」と、ふと考えることがあります。
少し前、2023年の春に開催されていた「不快のデザイン展」という企画展を見に行ったことがありました。
参考:世の中を良くする不快のデザイン展 - デザイン・アートの展覧会 & イベント情報 | JDN
展示されていたのは、あえて濡れた感じを出すおむつ、苦いおもちゃ、踏切の遮断機…。
一見すると「なんでこんな不親切な作りに?」と思ってしまうようなものばかりです。
しかし、よく見ていくとそれぞれが "気づかせるための不快" として設計されていることを知りました。
わざと不快にすることで、ユーザーに考えさせたり、気づかせたりする。
あえて不便にすることで、行動の意味やプロセスをより意識させる。
そうした体験を通じて、こんな問いが浮かびました。
「快適でスムーズなことが、必ずしも良い体験とは限らないのでは?」
今回は、「不便益」(後述)や展示体験をもとに、"ちょっと不便" や "ちょっと不快" がもたらすUXの価値について考えてみたいと思います。
「不便益」から考えるUXの逆説
「不便益(ふべんえき)」という考え方をご存じでしょうか?
京都先端科学大学の川上浩司教授が提唱しているもので、ざっくり言うと——
「不便だからこそ得られる利益や価値がある」 という逆説的な視点です。
たとえば、こんな例が紹介されています。
| 事例 | 効果 |
|---|---|
| あえて分かりにくくした地図 | 調べながら道を覚えるので、記憶に残りやすい |
| 足で漕ぐ車椅子 | 自分の足で移動ができて、楽しい(リハビリ効果もある) |
| でこぼこした園庭 | 転びやすくなっていることで、どうすれば転ばないかを自分で考える |
どれも「使いやすくない」んだけど、だからこそ使う側は考えたり集中したり記憶したり意識が向いたりする。便利すぎる"モノ"や"コト"は、時になにも残らない体験になってしまうことがあります。
ただし、ちょっと手間があることで、自分の行動や目的に対して意識が働きます。これが「不便益」という考え方の面白いところです。
参考:川上浩司(2017)『不便益という発想~ごめんなさい、もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら、不便をとり入れてみてはどうですか?』インプレス
この「不便益」の視点は、UX設計にも応用できると感じています。
たとえば——
| 具体的な対応 | UX設計時の意図 |
|---|---|
| ログインフローにワンクッション置く | セキュリティ意識を高めたり、操作の意図を明確にする |
| 設定項目にあえて迷いを残す | ユーザーに考える余白を与えることで、自分で選んだという納得感が生まれる |
| あえて非効率なチュートリアル | 最短距離よりも試して覚えることで、記憶に残る体験に |
もちろん、すべての場面で不便を取り入れる必要はありません。
ただし「あえてちょっとだけ遠回りさせることで、体験が豊かになる」という視点は、UXを考える上でひとつのヒントになると思います。
「不快のデザイン展」で感じた気づきの再設計
「不便益」という考え方を知ってから、過去の体験を思い返して「なるほど、そういうことだったのか」と腑に落ちた出来事があります。
それが、冒頭でもお伝えした「不快のデザイン展」での体験です。 一見すると "使いづらさ" や 心地の悪さ" を感じるような展示ばかりでしたが、 あれこそがまさに意図的に仕掛けられた "UXとしての不快" だったのだと思います。
展示の中でも、特に印象に残ったのが「不快や不便が、ユーザーの行動を引き出す設計」でした。
たとえば、あるおむつには、あえて "濡れた感じ" を残す工夫がされていました。
通常のオムツはできるだけ快適にサラッと仕上げるのが良いとされますが、このオムツは違います。
あえて不快感を感じることで、子どもが「濡れるのがイヤ」と思うようになり、トイレトレーニングをスムーズに進めるための設計になっているのです。

他にも、 Nintendo Switchのゲームカードには苦味成分が塗られていることをご存じでしょうか?
子どもの誤飲を防ぐために、あえて苦く不快に感じる味をつけているそうです。
これもまさに「使わせない」ためのUX。"触らせない" "飲み込ませない" ことが成功となる体験なのだと知りました。
上記の取り組みは公式サイトのQ&Aにも記載があります。
【Switch】ゲームカードをさわった手をなめたら、苦い変な味がしました。健康に害はありませんか?

また、踏切のデザインには、あらゆる不快要素が安全のために詰め込まれていることを知って驚きました。
- 黄色×黒のしま模様 → JIS安全色で「注意・警告」を表す黄色と、対比色(安全色を引き立てる色)の黒色の配色
- 遮断かんの高さ → 約0.8mで、小学校低学年の目線に合わせた設計になっており、またぎにくく、くぐりにくい高さでもある
- 「カンカンカン」という警報音 → 人間が最も不快と感じる "短9度音程" で構成され、音そのものが危険を伝えている
一見、全部「イヤなもの」に見えるのですが、それぞれがちゃんと目的に沿って不快さを設計しています。

こうしたデザインに共通しているのは、ユーザーの行動や感情を能動的に動かすために、不快や不便をあえて使っているということです。
UX設計というと、つい「スムーズで快適な体験」を目指してしまいがちですが、時には、少しの違和感や不快さがユーザーの "気づき" や "変化" を促す体験になるのだと気づかされました。
「デザインあ展neo」と「考える余白」
もうひとつ印象的だったのが、「デザインあ展neo」(2025年4月18日〜9月23日開催)での体験です。
この展示では、"モノそのもの" よりも、「そのモノを通じてどんな "行為" が生まれるか」に焦点が当てられていました。
デザインとは、単に「きれい」「かっこいい」だけではなく、人の行動や関わり方そのものをかたちづくるものなんだ、ということを体感的に学べる展示でした。
たとえば、イスがそこにあるから「座る」、蛇口があるから「ひねる」、道があるから「進む」。 私たちは普段、あまり意識せずに動作を繰り返していますが、その背景にはデザインが人の行動をそっと導いているという事実があります。
展示を通じて感じたのは、"良いUX" とは、ユーザーの行為をどうデザインするか、ということと深く結びついているということでした。
そしてそれは「快適さ」や「効率」だけではなくて、あえて立ち止まらせたり、迷わせたりすることで生まれる "気づき" や "納得" も含めた設計なんだと思います。

※モノと動詞の関係を表した展示
UX設計における "行為のデザイン"
デザインあ展neo を通して感じたのは、「行為をデザインする」という視点は、UX設計そのものに直結しているということです。
私たちが普段つくっているプロダクトやサービスも、突き詰めれば「ユーザーがどんな行動を取るか」を設計する仕事です。
- フォームのステップを1つずつ分けることで、「入力する」から「完了する」までを安心して進められるようにする
- あえて確認画面を設けて、「送信する」ことの意味を再確認してもらう
- 成果が見えるグラフを置くことで、「記録する」行動を継続してもらう
こうした設計のひとつひとつは、まさに行為を丁寧にデザインしているとも言えます。
そして時には、「あえて遠回りにする」「あえて迷わせる」といった手段が、結果的に"考える""選ぶ""気づく"という行為を引き出し、体験を深くすることにつながることもあります。
UX設計において、「便利・簡単」だけを追い求めすぎないこと。 それが今回の体験を通じて、あらためて考えるようになったポイントです。
おわりに
UXというと、何か専門知識やスキルを必要とすると思われがちですが、実はその種は私たちの日常のあちこちに転がっています。
- 「あれ、なんか使いにくいな」と思ったとき
- 「つい、こっちの道を選んでしまった」とき
- 「これ、不快だけどなんか印象に残るな」と感じたとき
そういった、小さな「おや?」や「つい」が、実はUXを考えるうえでのヒントになることがたくさんあります。
今回紹介した「不便益」や「不快のデザイン」、「行為のデザイン」という視点も、そうした日常の違和感に目を向けることで気づけたものばかりでした。
UXを考えるというのは、人の行動や感情に寄り添うことでもあります。 そして時には、「不快」や「遠回り」といった要素が、その人らしい体験を引き出すきっかけになることもあります。 だからこそ、便利さや快適さだけではなく、"なんか気になる" を見逃さないことも、UXを育てるうえでとても大切なんじゃないかと思います。
※人が動くしくみについては、以下の本も非常に学びが多くて内容も面白かったのでぜひ読んでみてください!
玉樹 真一郎(2019)『「ついやってしまう」体験のつくりかた 人を動かす「直感・驚き・物語」のしくみ』ダイヤモンド社
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
アジアクエスト株式会社では一緒に働いていただける方を募集しています。
興味のある方は以下のURLを御覧ください。