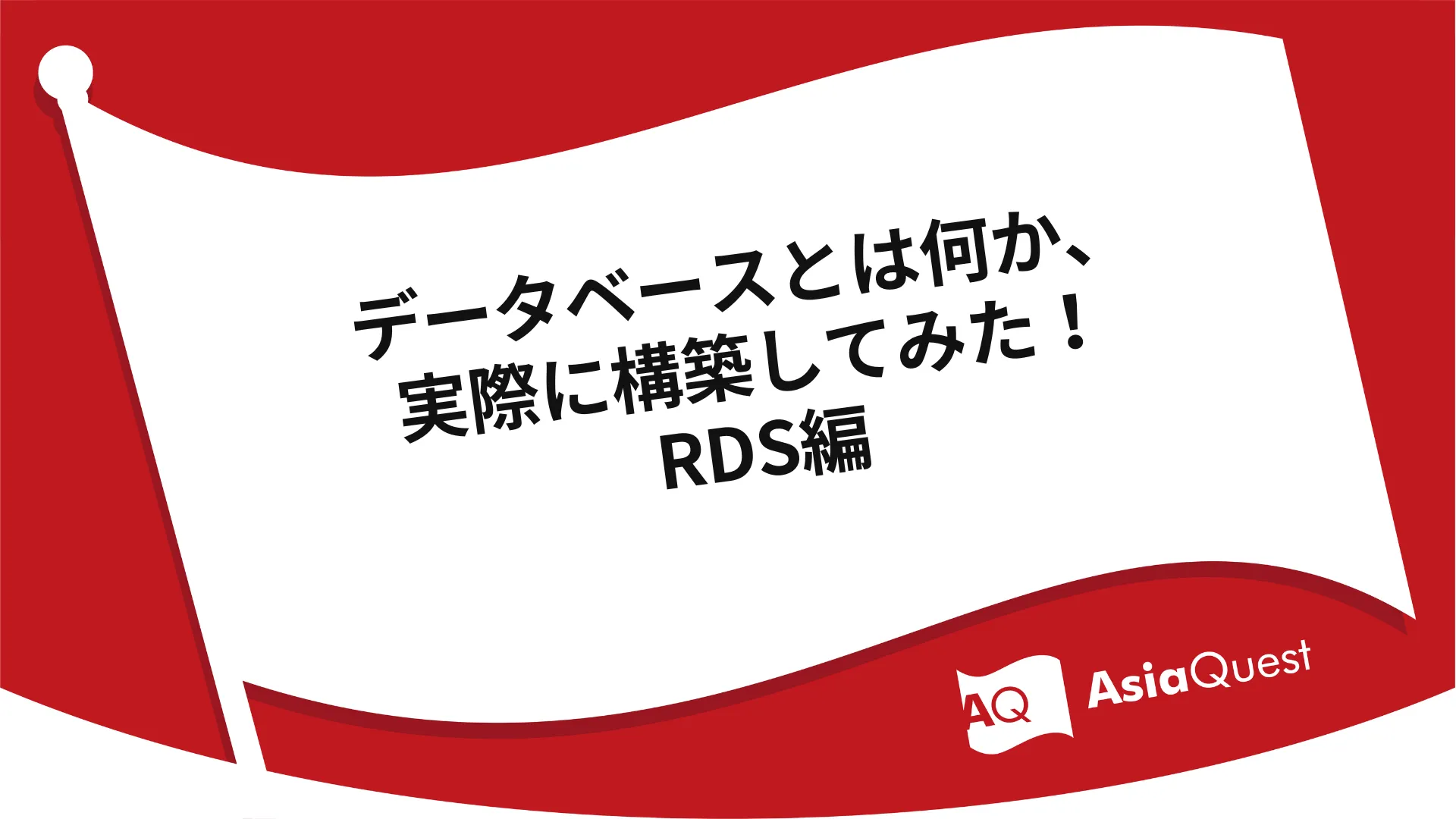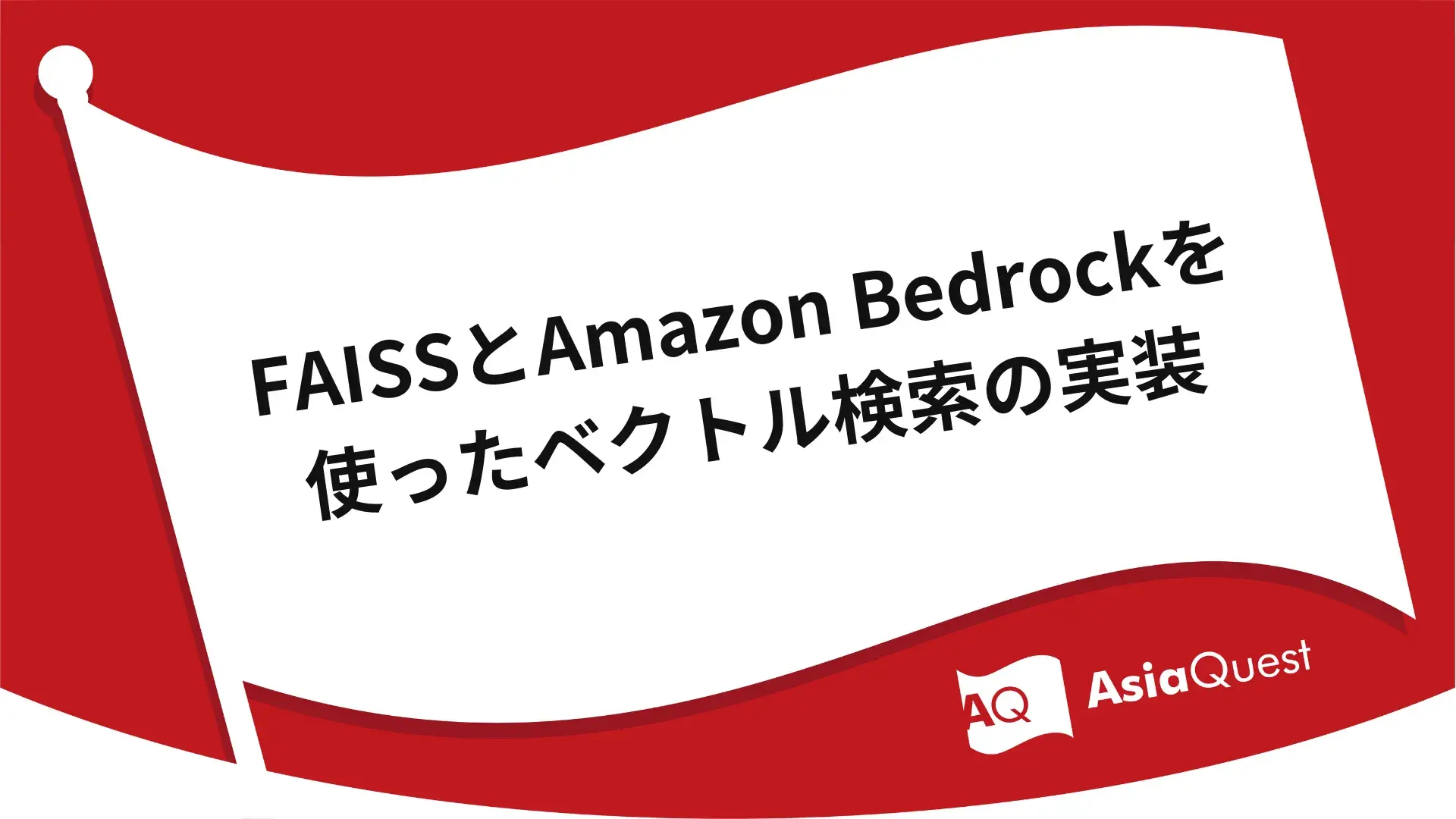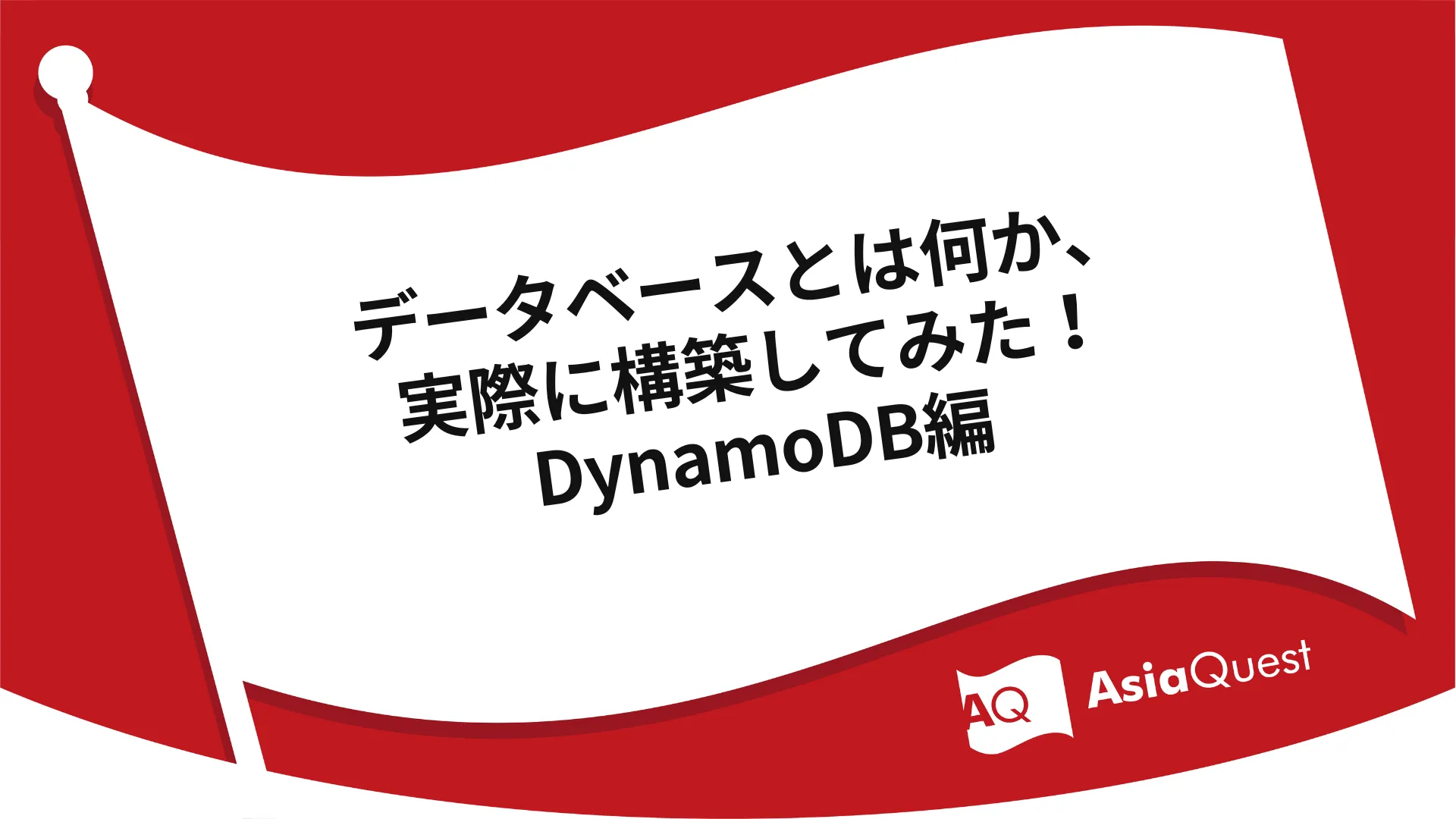初めてのAmazon Q Developerでゲーム開発にチャレンジ!!

目次
はじめに
はじめまして。
クラウドインテグレーション部25新卒の安藤です。
2025年6月27日、当社東京オフィスで開催された『初めての(再入門)Amazon Q Developer ~進化したAmazon Q Developerを触ってみよう~』というトレーニングに参加しました。
今回初めてAmazon Q Developerに触れましたが、本トレーニングに参加をしたことによって、Amazon Q Developerが持つ様々な可能を学び、体験する、素晴らしい機会でした。
今回は、私がこのトレーニングでどんなことを学び、体験したのかを紹介していきたいと思います。
トレーニング概要
『初めての(再入門)Amazon Q Developer ~進化したAmazon Q Developerを触ってみよう~』は、アジアクエストでのクラウド活動推進の一環として開催されたトレーニングです。
「AIコーディングを業務で活用していきたい」、「興味はあったけれど触ったことがない」といったAIコーディング初心者~中級者を主な対象としており、サービスについて学ぶ座学に加えて、実際に活用をしてみるワークショップも交えた体験型研修として実施されました。
講師にアマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(以下、AWS Japan社)の方をお招きし、Amazon Q Developerの機能紹介やユースケースについて直接お話を伺える貴重な機会でした。
- トレーニングタイトル:初めての(再入門)Amazon Q Developer ~進化したAmazon Q Developerを触ってみよう~
- 開催日時:2025/6/27(金) 17:00-19:00
- 開催場所:アジアクエスト東京オフィス
- アジェンダ:
- Amazon Q Developerのサービス紹介、ユースケースの紹介(50分)
- Amazon Q Developer CLIハンズオン(50分)
- 制作したゲームの発表(15分)
- 講師:
- AWS Japanパートナーソリューションアーキテクト(PSA)荒巻氏、廣岡氏、鍵谷氏
トレーニング参加の経緯
そんなトレーニングに私が参加しようと思った大きな理由が「Amazon Q Developerの活用を体験できるから」です!
Amazon Q Developerのことはトレーニング開催以前より知っており興味はあったものの、実際にどのように使えるのか、また使うことで何ができるようになるのかについてはあまり良く理解しておらず、雲の上の存在のように感じていました。
その際に今回のトレーニングが開催される話を耳にしました。
Amazon Q Developerに興味がある人向けという難易度ももちろんですが、何よりもワークショップで実際に体験することもできる、というところがすごく魅力的でした。
「習うより慣れろ」ということわざもあるように、知識として学ぶよりも、実際に手を動かして体験したほうが理解しやすいということもあり、この機会を逃してはならない、とすぐさま参加を決めました。
実際、このトレーニングを受けたことで、Amazon Q Developerを使うことに対するハードルが大きく下がり、それ以降の業務の様々な場面で活用するようになったので、初めてのきっかけとしてとても良い機会だったと感じています。
ここからは、そんなトレーニングの中で私の印象に強く残っていることや、ワークショップで体験したことを中心にお伝えしていきます!
座学パート ~Amazon Q Developerとは~
前半では、「AIエージェントとAI駆動開発の説明」と「Amazon Q Developerのサービス紹介、ユースケースと活用方法」について説明がありました。
中でも、特に驚きを感じた3点について紹介します!
AIエージェントはタスクを分割して思考、実行ができる!
1つ目の驚きは、何と言ってもAIエージェントが持つ能力の高さ!!
AIエージェントってそもそも何?という人に向けて簡単に説明すると、「ある与えられた目的を達成するために自律的に行動をするシステム」のことです。
この自律的というのが最大のポイントで、AIエージェントは、複雑なタスクを受け取るとそれを小さなタスクへと分割し、1つずつ順序立てて実行していきます。
例えば、「Webアプリケーションを作って」という曖昧な指示を与えると...
- 要件を整理・確認する
- 必要な技術スタックを選定する
- プロジェクト構造を設計する
- 実際にコードを書く
- テストを実行する
- 問題があれば修正する
このように、AIエージェントは指示を達成するために必要なプロセスを自身で考えて分割して、行動してくれます。
Amazon Q DeveloperもこのAIエージェントの機能を持っているので、開発者は最終的なゴールを伝えるだけで、複雑な開発工程のサポートをしてくれます。
Amazon Q Developerで構成図が生成できる
2つ目の驚きは、Amazon Q Developerで構成図を作れるということ。
構成図といえば、アイコンや図形を選び1つ1つ配置して、リソースの通信経路を線で繋いで...といったように、地道な上に時間のかかってしまう作業。
Amazon Q Developerであれば、そんな大変な構成図作成も手厚くサポートしてくれます!
例えば、次のような指示を与えてみると...?
3層WebアーキテクチャのWebシステムのAWS構成図をdrawioで作って

待つこと10数秒、あっという間にこのような構成図を生成してくれました。
ある程度の手直しは必要ですが、それでも1から作るよりも大幅に作業時間を短縮できる――そんな機能をAmazon Q Developerは持っているんです!
AWSのインフラ構築をAmazon Q Developerに任せられる!?
3つ目の驚きは、実際にAWSインフラ構築までサポートしてくれること。
Amazon Q Developerは、当然ながらAWSに精通をしており、エンジニアの開発工程を包括的に支援してくれます。
特に印象的なのは、要件定義書を読み込んで、CloudFormationやTerraformなどのIaC(Infrastructure as Code)のコード開発をサポートしてくれる点です。
従来であれば、要件定義 → 設計 → 実装 → テスト → デプロイという長いSDLC(ソフトウェア開発ライフサイクル)を経る必要がありましたが、Amazon Q Developerを活用することで、このプロセスを大幅に迅速化することができます。
さらに、構築時や構築後に発生したエラー分析やトラブルシューティングもプロンプトで指示を与えると、クラウド環境とリソース情報に基づいて、異常検知と調査のための情報を収集して原因を推定し、解決策を提示してくれます。
通常、調査や情報取集に膨大な時間や手間がかかるところを、Amazon Q Developerの機能のサポートによって運用の負担軽減や作業効率の向上に繋がり、エンジニアの強い味方となってくれそうです!
インフラエンジニアとなって間もないながらも、「要件を伝えるだけでインフラを自動構築できる時代がきたこと」と強く実感する、衝撃を受けたお話でした。
衝撃を受けたのと同時に「手を動かすエンジニア」から「価値を創り出すエンジニア」への進化が求められことも強く感じました。
ワークショップ ~Amazon Q Developer CLIでゲーム制作~
座学の後は、トレーニングの目玉ともいえるワークショップです!!
今回は複数人のチームに分かれ、Amazon Q Developer CLIを使い、HTMLとJavaScriptで動く簡単なゲームコンテンツ制作を体験しました。
どんな指示を与えると想像したゲームが作れるのか。
普段から使ってる人はもちろん、初めて使う人も、様々な試行錯誤を重ねて0からコンテンツが作られていく過程を楽しみながら、Amazon Q Developer CLIの使い方を学びました。

私達のチームでは、出現した敵キャラが放つ弾を避けつつ、自分も弾を打って敵を倒してスコアを稼ぐ「弾幕シューティングゲーム」の制作にチャレンジしました!
ゲームルールの指示や、UIデザインのイメージなど、ゲームの方向性の指示を与えつつ、完成したゲームを踏まえて都度修正点の指示も与えていきました。
そうして完成したのがこちら!!
ポイントは、相手の弾の形がアルファベットの「Q」の形をしているところ。
Amazon Q Developerらしい何かをゲームに取り入れてみようと、興味半分で「弾の形状はアルファベットのQの形にしてほしい」と指示を与えてみたところ、思っていた以上に「Q」の形にしてくれたので驚きました。
こういった「ふと思いついたこと」をそのまま気軽に実装できるのも、すごく面白いところだと思います。
ここからは、実際にAmazon Q Developer CLIに触れたことで学んだこと、気付いたことをいくつか紹介していきます。
具体的な指示ほどうまくいく
ワークショップでAmazon Q Developer CLIを使ってみて、一番に実感したのが指示の出し方によって、生成される内容が大きく変わるということでした!
最初に行った指示は、「弾幕シューティングを作ってほしい」といったシンプルな一言。これだけでもある程度は動くゲームを作ってくれたのですが、敵も自分も無機質な図形のデザインであったり、スコア機能などのゲーム性もほとんど無い無骨なゲームとなってしまいました。
そこで、「相手の弾は幾何学模様に動く」「ライフを3つ持ち、なくなるとゲームオーバー」などの具体的な指示を与えて作り直してもらったところ、途端にゲームらしさがグレードアップ。イメージに近いゲーム性の実装に成功しました!
さらに、「相手の弾の形をアルファベットのQにする」「デザインをSF風にする」などとビジュアルも明示してみることで、よりイメージにあったゲームを完成させることができました!
相手がAIとはいえ、複数の解釈が取れるような曖昧な表現で指示を与えてしまうと、思うように生成してくれない、まさにAIとのコミュニケーション力が開発の成功を左右するということを実感しました。
コーディング言語知識がなくてもコンテンツ制作が可能
また、ゲームを動かすコード知識が無くても、自然言語の対話のみでゲームコンテンツが完成したということにも、とても驚きました。
私自身、HTMLやJavaScriptの知識はあまり持ち合わせていない初心者であり、何をどうすればゲームが動くのか、わからないことばかりでした。
しかし今回のワークショップでは、前述したような実装してほしいことを自然言語で表現した指示だけで、Amazon Q Developer CLIが動くコードを生成して、ゲームを開発してくれました。
従来であれば、コンテンツ開発には開発言語の知識や、動きのアルゴリズムへの理解など、専門的な知識が必要不可欠でした。
しかし今回、「何を作りたいか」というアイデアさえあれば、誰でも気軽に想像したものを形にすることが可能になるということを実感しました。
まとめ
今回のトレーニングは、AIエージェントとAmazon Q Developerについて学ぶ座学パートと、実際に手を動かして体験をするワークショップの2部構成で開催されました。
知識としてのインプットだけでなく、ワークショップを通して実際にどのように使うことができるのかを体験したことで、今までAmazon Q Developerに触れたこととのない人でも、便利なところや面白さを実感することができるトレーニングでした。
今後、このAmazon Q Developerを様々な場面で活かしていきたいと思います。

ワークショップの最後に制作したゲームコンテンツの発表を行う機会を頂き、Amazon Qステッカーとピンバッジを頂きました!
アジアクエスト株式会社では一緒に働いていただける方を募集しています。
興味のある方は以下のURLを御覧ください。