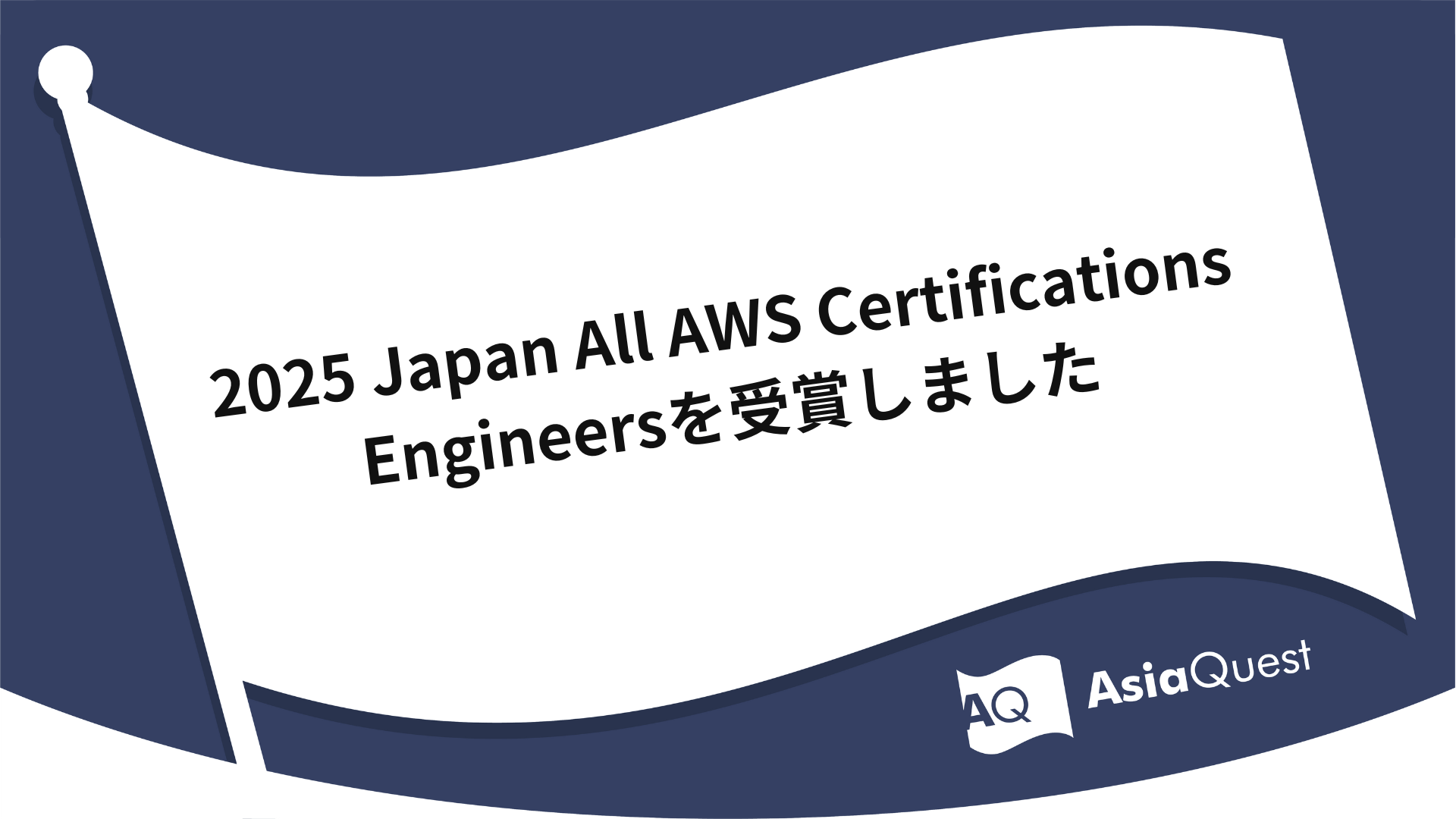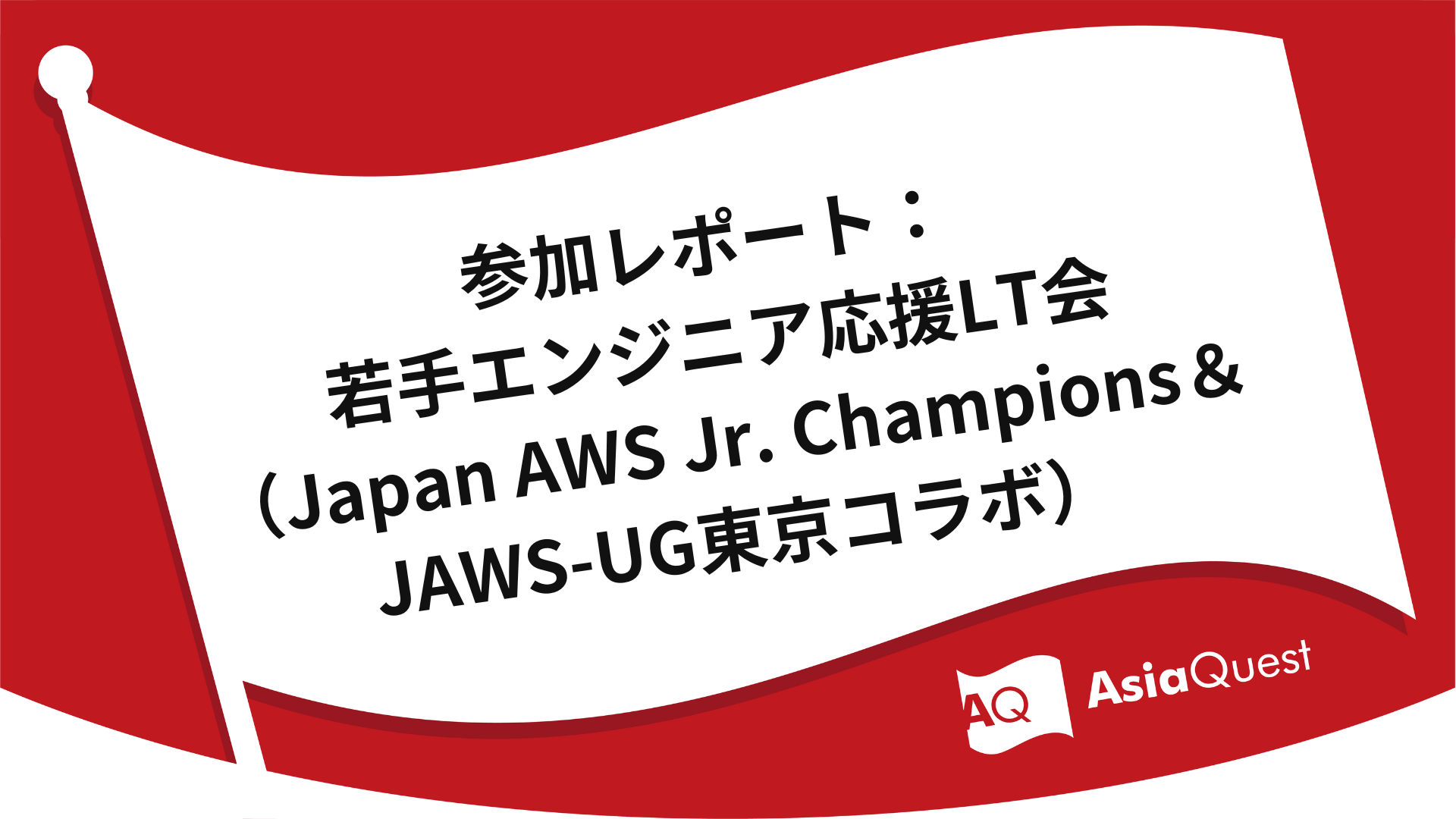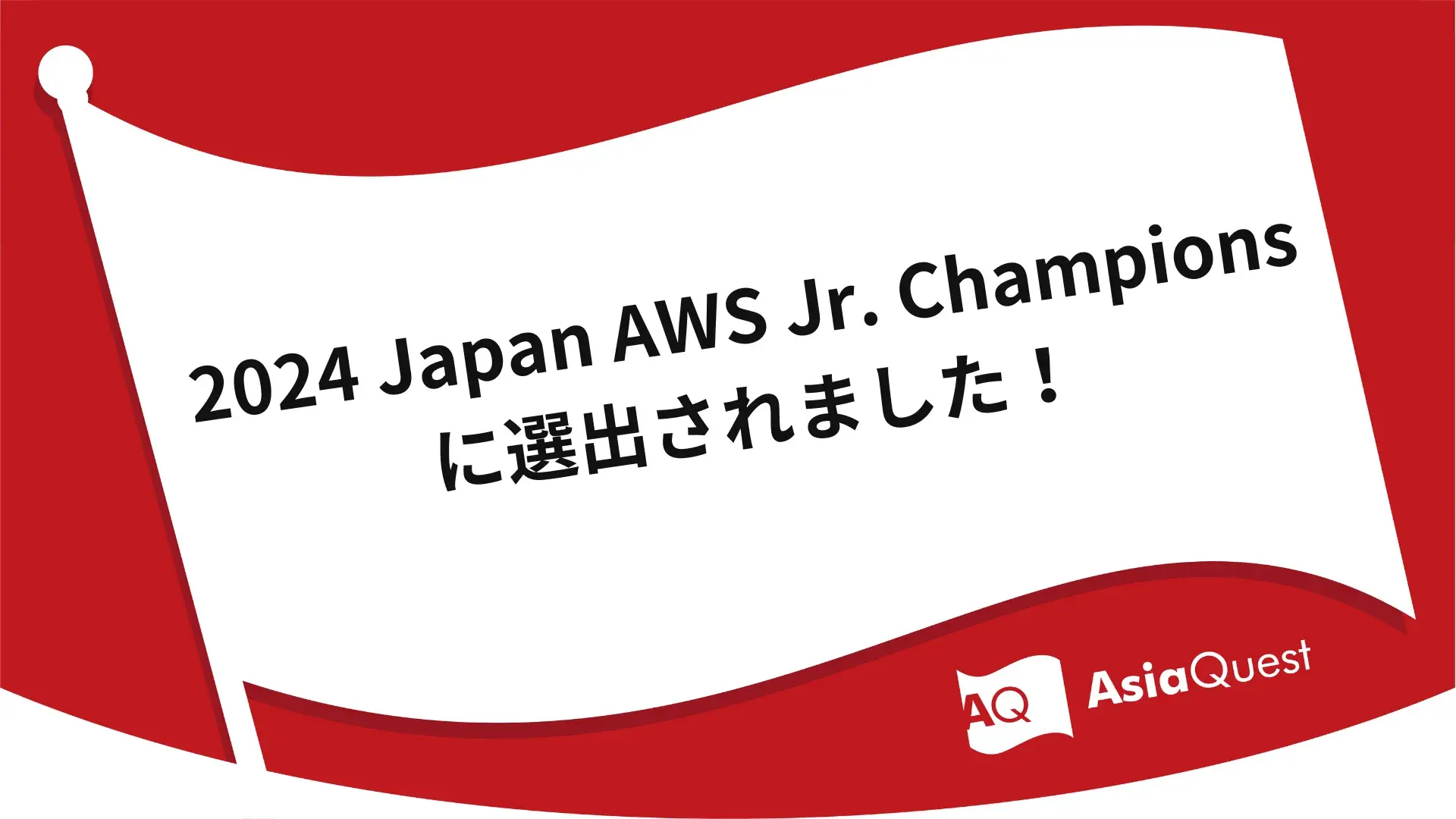2025年 AWS全冠 + Jr. Champions 体験談 ―非エンジニアの挑戦
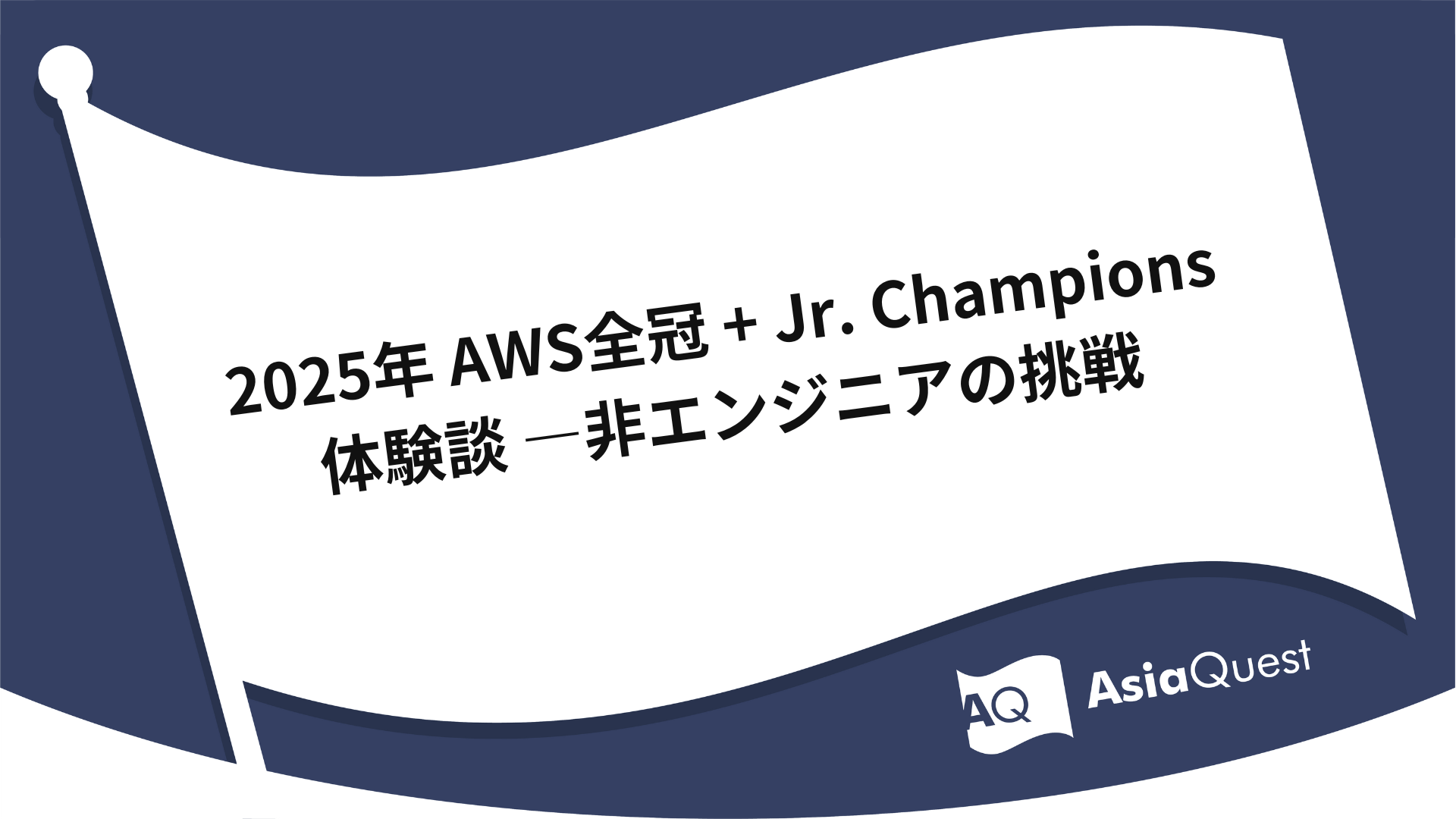
目次
1. はじめに
この体験談を書いた理由
こんにちは。デジタルイノベーション部の足立です。
私は非エンジニアでありながら、AWS全12種類の認定資格(通称「全冠」)を取得し、「2025 Japan AWS Jr. Champions」「2025 Japan All AWS Certifications Engineer」の2つに選出されました。
この体験談を書こうと思ったのは、私のような非エンジニアでも、地道な努力を続けることで道が開けるということを、同じような境遇の方々にお伝えできればと思ったからです。特別な才能や経験があったわけではなく、継続することや周囲のサポートを得ることの大切さを実感したので、それが少しでも参考になれば幸いです。
AWS Jr. Champions制度について
AWS Jr. Championsは、APN参加企業の社会人歴1~3年目の若手エンジニアを対象とした日本独自の表彰プログラムです。AWSを積極的に学び、自らアクションを起こし、周囲に影響を与えている若手エンジニアを選出し、コミュニティを形成することを目的としています。
任期は1年間で、2025年度は113名が選出され、選出者にはJapan AWS Jr. Champions Meetupへの参加権や、AWSパートナー限定のテクニカルセッションへの優先参加権などの特典が提供されます。この制度は、若手エンジニアの成長を促進し、将来的にAWS AmbassadorsやJapan AWS Top Engineersへのステップアップを目指す人材を育成する役割を果たしています。
All AWS Certifications Engineers制度について
All AWS Certifications Engineersは、APN参加企業に所属し、AWS認定資格を全て保持しているエンジニアを対象とした表彰プログラムです。2025年には新たに3つの認定資格が追加され、全12種類の認定資格を取得することの難易度は非常に高くなっています。
2025年度は1,633名のエンジニアが受賞され、受賞者にはAWSパートナー向けテクニカルセッションの優先参加権と副賞が提供されます。この制度は、幅広く高度なAWSテクノロジーの技術基盤を維持・向上させ続けているエンジニアを表彰し、専門的な知見を活かしたさらなる活躍を期待するものです。
2. なぜ私は「AWS全冠」を目指したのか?
新卒入社時の焦りと不安
私は建設業界のお客様を相手に働いており、日常業務は建設現場で使用する品質管理システムの検証や運用サポート、そして開発ベンダーとのシステム開発のやり取りです。エンジニアポジションではないため、業務ではクラウドの設計や構築を直接行う機会はありません。
新卒1年目から現在の案件に携わっていますが、右も左もわからない状態で、なんとか業務についていこうと、かなり焦りを感じていました。エンジニアではない自分が、ITシステムに関わる業務で価値を提供できるのか。技術的な知識が不足している中で、何か一つでも武器が欲しいという思いが強くなっていきました。
業務課題を通じて感じた技術理解の必要性
そんな中で最も印象に残っているのは、開発ベンダーとのやり取りで遭遇したシステムの遅延トラブルです。
オートスケーリングを実装していたにも関わらず、処理に時間がかかってしまう問題が発生しました。当時の私は「オートスケーリングを設定すれば処理速度が改善する」と考えていましたが、実際にはサーバーを増やしても根本的な解決にはならず、適切なアーキテクチャ設計が重要だということを学びました。
このトラブルを通じて、技術的な課題に対して表面的な理解しかできていない自分に限界と歯がゆさを感じ、より深い技術理解の必要性を痛感したのです。
AWS学習開始と魅力の発見
そのような不安と課題意識から、技術的な武器を身につけたいという思いが強くなっていきました。数ある技術の中からAWSを選んだ理由は、クラウドへの興味と、非エンジニアでも取り組みやすい学習環境があったからです。特に、AWSの無料枠や豊富なドキュメント、そして実践的なハンズオン環境が、私のような初学者にとって魅力的でした。
なぜAWSのクラウドに魅力を感じるようになったのか。それは、実際に自分で環境を立ち上げて触ってみたからこそです。非エンジニアでも簡単にアプリを作成できたり、サーバーを構築できたりする手軽さ、そして様々なサービスを自由に組み合わせることで多様な応用が効く柔軟さを実感できました。実際に触れてみることで、AWSの設計思想やベストプラクティスが、単なる技術知識を超えて、複雑な課題を効率的に解決するための思考プロセスそのものだということに気づきました。
3. 全冠取得への道のりで感じた葛藤と喜び
印象深い試験での苦労と達成感
業務でAWSを扱っていないということもあり、概念の理解と実装の間にはギャップがありました。通勤時間(往復約2時間)を活用して問題演習を行い、休日には実際にハンズオン環境を構築してリソースの作成・削除を繰り返しながら学習しました。
特に苦労したのは、AWS Certified Advanced Networking – Specialtyの試験でした。オンプレミス環境との接続やVPN設定など、実際に触ることができない部分の理解が非常に困難でした。図解による理解が不可欠で、ネットワーク構成図を何度も描き直しながら、データの流れや設定の関係性を理解していきました。
非エンジニアならではの学習の困難さを感じる中で、生成AIをメンターとして活用する工夫も実践しました。最終的に、AWS認定の資格12個すべてを取得することができました。
取得した資格一覧
| 資格正式名称 | 取得日 | 取得時期 |
|---|---|---|
| AWS Certified Cloud Practitioner | 2022/8/6 | 入社前(内定段階) |
| AWS Certified Solutions Architect – Associate | 2023/2/18 | 入社前(内定段階) |
| AWS Certified Developer – Associate | 2024/3/20 | 入社後 |
| AWS Certified SysOps Administrator – Associate | 2024/3/24 | 入社後 |
| AWS Certified Data Engineer – Associate | 2024/6/1 | 入社後 |
| AWS Certified Solutions Architect – Professional | 2024/8/5 | 入社後 |
| AWS Certified Security – Specialty | 2024/9/23 | 入社後 |
| AWS Certified Advanced Networking – Specialty | 2024/12/26 | 入社後 |
| AWS Certified Machine Learning Engineer – Associate | 2025/1/11 | 入社後 |
| AWS Certified AI Practitioner | 2025/1/13 | 入社後 |
| AWS Certified Machine Learning – Specialty | 2025/2/8 | 入社後 |
| AWS Certified DevOps Engineer – Professional | 2025/3/9 | 入社後 |
入社前の内定段階でCloud PractitionerとSolutions Architect Associateの2つの資格を取得し、入社後は約10か月の期間で残り10個のAWS認定資格を取得しました。
コミュニティの力と価値の実感
業務でAWSを扱っていない私にとって、AWSの実践的な知見を得るために、まずはオンラインの情報収集から始めました。しかし、書籍やドキュメントだけでは、実際の運用現場での課題やベストプラクティスを理解するのは困難でした。
そんな中で出会ったのがJAWS-UGでした。JAWS-UGとは、日本最大級のAWSユーザーグループで、全国各地で技術勉強会やハンズオンイベントを開催しているコミュニティです。独学では得られない貴重な視点を獲得する機会となり、特に実践者の知見に触れることで、理論と実践のギャップを埋めることができました。
常にアップデートが繰り返される膨大なサービス群の中で、質の高いコミュニティに所属し、切磋琢磨できる環境。これが私の学習を大きく加速させてくれた要因の一つでした。
4. AWS Jr. Champions への挑戦
AWS Jr. Champions を目指すきっかけ
そうして自己研鑽として資格勉強などに励むうちに、中級レベルのアソシエイト資格を全て取得しました。すると、当時のコンサルティング部の部長から、部署内での資格推進をやってくれないかと依頼されました。
「ぜひやらせてください」と引き受け、一人ひとりにヒアリングをしながら、「なぜAWS認定がその人に役立つのか」「どのように勉強を進めればいいのか」「どうやって業務に役立てていくのか」といったことを考え伝えました。
その結果、当時は20人ほどの部署でほとんどいなかったAWS認定の取得数を、2か月で合計12個まで増やすことができました。
この活動がクラウドインテグレーション部の部長の目にとまり、「AWS Jr. Championsという制度があるから、目指してみないか」とお声がけいただきました。当時はAWS Jr. Championsがどんなものかよく分かっていませんでしたが、「面白そうだからやってみたい」という気軽な気持ちで目指してみようと決めました。
しかし、詳細を調べてみると、公式ホームページには「若手エンジニアのロールモデルとして、コミュニティをリードできるような存在」と書いてあり、自分にそのような活動が務まるのかどうか、非常に不安を覚えました。
コミュニティイベントでの転機
転機となったのは、2024年10月にAWS目黒オフィスで開催された「若手エンジニア応援LT会( Japan AWS Jr. Champions&JAWS-UG東京コラボ)」への参加でした。
私は翌年のAWS Jr. Champions選出を目指して参加しました。同世代の若手が積極的にアウトプットし、実務課題に技術を応用している姿に刺激を受けました。AWS公式情報の翻訳と要約を社内ブログレビューに活用した事例や、コミュニティ活動を通じた新人教育の事例が紹介され、「自分もこうしたコミュニティで成長し、得たものを還元したい」と強く感じました。
特にAWS Heroのみのるん(御田 稔)さんの「社外の広い世界に一歩踏み出そう!」というメッセージに勇気づけられ、アウトプットの重要性を再認識しました。
このあたりから「自分に務まるのかどうか」ではなく、「成長してJr. Championsとしての役割が務まるようになりたい」と考えるようになりました。
イベント後には、ブログ執筆やconnpassの勉強会、JAWS-UGでの登壇などを積極的に行っていきました。例えば、JAWS-UG茨城×Education-JAWSコラボイベントでは「技術職じゃない私がAWSにハマった話」というタイトルで発表し、AWSのYukkiさんから「自分の言葉で感情を伝えていて良い発表だった」と言っていただけました。
Jr. Champions選出の瞬間
そのように半年近く活動を続け、2025年3月に申し込みが完了しました。
そして、2025年6月25日、AWS Summit Japan 2025の表彰セレモニーで「2025 Japan AWS Jr.Champions」選出者として自分の名前がスクリーンに映し出されました。

AWS Jr.Championsに選出された事を実感し、感激と嬉しさが込み上げてきました。しかし同時に自分の実力以上の肩書きを背負っていると感じたのも事実です。大事なのは、その肩書きを使ってこれから1年間、何をしていくのか。この表彰の重みに見合う存在に、自分を成長させていけるかどうか。そうしたことが問われていくのだと思います。
 弊社の2025 Japan AWS Jr. Champions。矢内(左)と足立(右)
弊社の2025 Japan AWS Jr. Champions。矢内(左)と足立(右)
5. Jr. Champions として取り組みたいこと
AWS Jr. Champions の制度への想い
AWS Jr. Championsの制度は今年で3年目です。1年目、2年目の先輩たちがアウトプットを続け、若手に還元しようという意志があったからこそ、この制度が続いてきて、今、自分たちにバトンが渡っているのだと実感しています。
私がこれからできることは、自分自身のアウトプットはもちろんですが、このせっかくのコミュニティの力を最大限に利用して、若手エンジニアにとっての機会をたくさん創出していくことだと感じています。
具体的な活動計画
若手やクラウド初心者向けのハンズオン・LT会を企画し、「初学者でもクラウド技術にアクセスしやすい環境作り」に取り組みたいと思います。技術的な詳細よりも「なぜクラウドが重要なのか」「ビジネスにどう活かせるのか」に焦点を当てたイベント企画を考えています。
私が非エンジニアの立場からAWS学習に取り組んできた経験を活かし、初学者の立場に立った学習ガイドを作成したいと考えています。技術的な背景がない方でも安心して取り組めるよう、段階的な学習方法や、つまずきやすいポイントなど体験談を交えながら体系化していきたいと思います。
また、部署横断の知見共有や勉強会を開催したいと考えています。私のクラウド専門部署ではない立場を活かし、橋渡し役としての価値を活かしていきたいと思います。
6. まとめ ― 読者のあなたへ
体験を通じて伝えたいメッセージ
この長い体験談を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。私がこの体験を通じて最も伝えたいのは、「技術的な背景がなくても、一歩ずつ積み重ねることで、誰でもクラウド技術の世界に参加できる」ということです。
私は特別な才能があるわけでもありませんが、本当に恵まれた環境にいることを実感しています。理解のある職場、そして素晴らしいコミュニティの皆様。こうした環境への感謝の気持ちを忘れずに、謙虚に学び続けていきたいと思います。
もしあなたが今、「自分には無理かもしれない」と感じているとしても、小さな一歩から始めてみてください。最初の認定試験、最初の勉強会参加、最初のコミュニティイベント参加。どんな小さな一歩でも、それが大きな変化のきっかけになる可能性があります。
これからAWS Jr. Championsを目指す人へ
この体験談を読んで、AWS表彰やコミュニティ活動に興味を持っていただけた方がいらっしゃれば、嬉しい限りです。私もまだまだ学習途中であり、皆さんと一緒に成長していきたいと思っています。
特に、非エンジニアの方や、技術的な背景に不安を感じている方がいらっしゃれば、私の経験が少しでもお役に立てれば幸いです。
最後に、支えてくださったすべての方々に感謝いたします。JAWS-UGコミュニティ、職場の同僚や上司、家族。皆様のおかげで今の私があります。
これからも、小さな挑戦が大きな変化につながることを信じて、共に歩んでいきましょう。
アジアクエスト株式会社では一緒に働いていただける方を募集しています。
興味のある方は以下のURLを御覧ください。



%E5%85%A8%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%83%E3%81%A8%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AB%E5%87%BA%E3%81%9F/20231207_DeepRacer_thum.webp)